第5章 産業廃棄物処理業における企業ブランドの展開
アンケート調査の結果,産業廃棄物処理業者に高価値ブランドが確立する萌芽がみられたので,ブランドについて焦点を絞り込んで考察をすすめることとする。
1 企業ブランドの定義と意義
(1) ブランドの定義と機能
ブランドについて,アメリカマーケティング協会は次のように定義づけている。「ある販売者の商品もしくはサービスを特定するための,あるいは競争者のそれから区別するための,名前,ことば,目印,シンボル,意匠,もしくはそれらの組み合わせ」
ブランドが表すものは,財貨の属性,財貨の効用,財貨の価値,財貨の文化的背景,財貨の人格,財貨のユーザーなどである(注[69])。たとえば,自動車に付けられたメルセデス・ベンツというブランドからは,高性能車(基本的属性),安定した高速走行(効用),高価格(価値),ドイツの厳しい気候,世界最古の自動車製造業者(文化的背景),金持ちではあろうが趣味は疑問(ユーザー)といった諸属性が連想される。一方,牛丼吉野家といえば,牛肉が載った丼めし(基本的属性),てっとり早く満腹になる(効用),抜群のコスト・パフォーマンス(価格),100年近い伝統,関東風に濃い目の味付け(文化的背景),比較的若い男子の好物(ユーザー)といった連想に繋がるだろう。
ブランドの本来の意味は,特定の商品やサービスを他から区別する機能をもった符号にすぎず,ブランドが表す商品の特性は一律ではない。価格という側面をみても,あるブランドは高価格であることを主張するであろうし,逆に廉価であることを主張するブランドもある。こうした多様な方向性を持ったブランドであるが,それを決定するのは,財貨の売り手であるブランド所有者の意図と,買い手やブランドを取り巻く社会である。そうした中で,特に財貨の価値が高いことを主張するブランドがある。いわゆる高級ブランドである。まず,高級ブランドが表す財貨の属性を考えよう。高級ブランドという語からは,真似が困難;高品質;高価格;希少性;知名度などの事柄が想起されるだろう。つぎに,高級ブランド財を購買して得られる効用を考える。その物理的効用は高級ブランド財とそうでないものの間で大差はないだろう。意味的効用は,高額な支出を正当化できる;精神的満足を得られる;購買に際しての吟味が不要である;それを消費・所有することを他人に自慢できるなどである。
ここで,財貨の効用と,財貨のコンセプトについて整理する。財貨の効用は,物理的効用と意味的効用から構成される(注[70])。このうち,物理的効用とは,その財貨が買い手に与える直接的な機能で,売り手が規定したコンセプトに基づいて形作られる。もう一方の意味的効用とは,その財貨を所有・消費することによって買い手が得るもので,感覚的・感情的な要素を含む総合的な評価である。売り手が設定するコンセプトの最終的な目標は,買い手が受け取る意味的効用を規定することである。売り手がコンセプトを実現するために行う活動は,先ずその財貨に物理的効用を組み込むことを主とする。次いで,その物理的効用を拡大し,目標とする意味的効用につなげるために,買い手に対して,その財貨を所有・消費するための環境整備や,情報的な働きかけを行う。このような売り手の活動の全体こそがマーケティング活動である。売り手のマーケティング活動が成功するということは,そのコンセプトが買い手および市場に評価されることであり,それは売り手の意図する形で,ブランドに財貨の諸属性,とりわけ意味的効用が結びつけられることを意味する。このようにして確立したブランドは,売り手から買い手に対する情報的活動の要素として活用されることになる。これらのことを図 28にまとめた。以上のことは,産業廃棄物処理取引ばかりでなく,産業財・消費財,物財・サービス財を問わず全ての財貨の取引について適用されるものである。図 28からは,ブランドの価値はコンセプトの反映であることが理解できるが,そのことから,ブランドの価値はコンセプトの持つ価値以上のものにはなり得ないことが解る。
以降,産業廃棄物処理サービスにおけるブランドを議論するが,高級ブランドという語を産業廃棄物処理サービスにそのまま適用できるか現段階では疑問である。よって,高価値ブランドという語を用いることとする。
(2) 産業財マーケティングにおけるブランドの位置づけ
産業廃棄物処理サービスを含む産業財の取引は,企業組織による合理的判断に基づくゆえ,ブランドに意味はないとの通念が存在する。産業財の取引は,セールスマンによる売り込みによるものであり,買い手の側も購買する財貨の要件を定義しコスト・パフォーマンス管理を厳密に行うため,消費財で行われるようなマーケティングやブランドは不要であるとの論である。
一方,産業財取引の特徴として,新規の取引関係を構築することが困難であることと,いったん取引関係が構築されれば,その後は長期取引の傾向にあることが指摘されている(注[71])。このことが産業廃棄物処理サービスについてもあてはまることは,既に述べたとおりである。国が進めている「優良産廃処理業者認定制度」は,産業廃棄物処理取引にオープンな市場を導入することであり,従来の安定取引の構造を取り払うことを意図しているものである。
一方,産業財は,建物・機械設備,原材料,そして維持管理・修理・作業財(MRO goods: Maintenance, Repair, Operation goods)に分類できる(注[72])。このうちのMRO財の特徴は,比較的小規模な業者によって供給されること;その選択はサプライヤーとの直接取引や社会的評判によってなされることである(注[73])。このようなMRO財の特性をもとに考えれば,MRO財マーケティングにおけるブランドの役割の小ささが強調されることになるだろう。そして,産業廃棄物処理サービスは,その定義においてばかりでなく,取引の一般的な特性においてもMRO財に該当する。なお,MRO財のことを知れば,オープンな市場がないことは産業廃棄物処理サービスだけの特殊な状態でないことが分かる。オープンな市場の形成を促進することが産業廃棄物処理業を良くすることがどうか,さらに具体的な理論的裏付けが必要であると考えられる。
以上は産業財マーケティングにおけるブランドの役割に対する主に否定的な見解を挙げてきた。一方で,日本企業は産業財ブランドを軽視して損をしていることの指摘もなされている(注[74])。日本の製造業は既に新興国に抜かれつつあり,一方でブランドやマーケティングで欧米企業との距離が開く一方だという。世界的なブランド上位は,たとえばIBMやGEのように産業財に多い。更に,やはり産業財サプライヤーであるインテルは,より進んだブランド戦略をとっているという。インテルは,特許をオープンにすることで追随する企業群を組織化しつつ裾野を拡げ,自社はブランド管理を巧みに行うことで,追随企業群からなるピラミッドの頂点に君臨している(注[75])。
このように産業財におけるブランドの位置づけについては,未だに混乱した部分はあるが,わが国でも「顧客の顧客」ブランド戦略が注目されるようになってきている(注[76])。たとえば,アパレル用の繊維素材ライクラ(注[77])や,自動車用内装材アルカンターラなどの事例である。加えて,勤労者にも身近に感じられるものとして,飲食店向けの調理用燃料である紀州備長炭のブランド戦略がある。
(3) ブランドの構成要素
ブランドを作るのは,一義的にはその財貨の売り手である。売り手は,財貨を販売するに際して,その財貨を識別するための標識として,名前や意匠その他のブランドを与える。これが商品ブランドである。また,自社を識別するために商標を設定するが,それはコーポレイト・ブランド(企業ブランド)である。物理的な標識としてのブランドから,ブランドが意味するもの,ブランドから想起されるものにまで分析の範囲を拡げると,名付けた者の意図だけでブランドの成立を説明しきれないことは明らかである。
まず,ブランドは,財貨の実体的側面と情報的側面とから構成されるといえるだろう。ひとつの物体があったとして,それだけではブランドは構成しえない。なぜならば,その物体を他のものと区別する必要があって初めてブランドの必要性が生まれるからである。その場合には,その物体が含む何か特殊な成分とか,特定の作者の手によるものといった情報を添えることで,その物体にブランドを付けることが可能になる。つまり,財貨の実体的側面と情報的側面は両方が揃うことでブランドが成立すると言える。ここで,情報については,その発信元は情報に操作を加えることがある。それは,売り手が買い手に対して,ブランドをこのように解釈して欲しいというガイドラインを示すものであり,具体的には製品の意匠デザインや広告といった財貨の意味的効用の方向を操作しようという努力である。総括的にブランド戦略と呼ばれるものである。
つぎに,ブランドを作る主体は,売り手だけではなく,それに買い手を加える必要があるということである。すなわち,買い手は,実体としての財貨の評価を基礎として,それに売り手が発信した情報や社会の評判などを加味してブランドの総合的な評価をする。つまり,前述のようにKotlerは,ブランドは6レベルの要素(財貨の属性・財貨の効用・財貨の価値・財貨の文化的背景・財貨の人格・財貨のユーザー)から構成されるとしているが(注[78]),これら要素のうち売り手の側が100%支配している要素は,「財貨の属性」だけである。「財貨の効用」に関しては,物理的効用は売り手が規定するにしても,意味的効用は財貨を所有・消費した買い手があってはじめて生み出される。そして,「財貨の価値」とは,「財貨の意味的効用」に他ならない。また,「財貨の文化的背景」以降の3要素も,大部分を買い手が作り出すものである。これらのことを見ると,ブランドを作る主体とは,売り手だけではなく買い手を加えて認識しなければならないことがわかる。
以上のことを総括すれば,ブランドとは財貨の広義の属性情報の集約であり,売り手と買い手の相互的作用を通じて形成されるものといえるだろう。これらのことを図 28に織り込むことによって,図 30が得られる。一方,アンケートの結果を因子分析して,産業廃棄物処理業者の評価を構成する因子が明らかになったので,その因子を図 30に適用すると,産業廃棄物処理ブランドの構成を詳らかにする図 31が得られる。
図 30 ブランドの構成
図 31 産業廃棄物処理ブランドの構成
産業廃棄物処理ブランドの構成を基礎知識として,A社とT社の業界内ポジショニングを試みた。すなわち,産業廃棄物処理ブランドの主要な構成要素である具体的業務処理能力とマーケティング能力をそれぞれグラフの縦軸と横軸とし,アンケート回答において優秀業者として評点を与えられている産業廃棄物処理業者の因子スコアをプロットしたのが図 29である。グラフからは,A社およびT社ともに突出した特徴は見出せず,この2つの産業廃棄物処理業者が多くの支持を集めていることの理由を知ることはできなかった。今回のアンケートで設定した評価項目に沿って見る限りでは,2社は言わば平均的な優等生である。両社のブランド力の形成には,アンケート質問項目では捉えられない要素,たとえば歴史,文化,あるいは累積経験量といったものが大きく影響していると考えられる。あるいは,2社が特徴に欠ける優等生タイプであることは当然かも知れない。すなわち,産業廃棄物処理サービスは産業財(生産財)として購入される。生産のために冷静な判断をすれば,堅実な優等生を選択することは妥当であろう。
図 29 A社とT社のポジション
(4) 総合評価としてのブランド
マーケティングの目的は,ブランド価値を高めることであると言っても過言でない。すなわち,マーケティングとは財貨の総合的な評価を高めることであり,ブランドこそ財貨の総合的な評価の反映であるからである(注[79])。
財貨の消費における物理的効用と意味的効用については図 28において説明したところであるが,消費財に関しては,その消費は物理的消費と意味的消費からなると言われるものの,産業財に関しては,このことがあてはまり難いとも言われる。しかし,産業財でも特にサービス財については,意味的消費に重みを置かないと消費メカニズムは説明しづらい。産業廃棄物について言えば,無形のサービスである産業廃棄物処理の物理的効用は廃棄物の除去であって,物理的効用そのものでは財貨の差別化は達成できない。産業廃棄物処理業者が提供する拡張サービスおよびその外側のサービス(図 9)と,事業者が抱く期待と満足感が合わさることで,事業者の中に意味的効用が生成する。つまり,産業廃棄物処理サービスでは,ブランド評価以前の財の性能評価においてさえ,コア便益より外縁方向の広い範囲のサービスが評価対象にならざるを得ない。その結果,産業廃棄物処理サービスの評価自体が総合評価となり,産業廃棄物処理サービスの評価に加えて更に他の評価の反映である産業廃棄物ブランドは,ヨリ広範囲の評価を総合しているものであるといえる。
2 産業廃棄物処理業における高価値ブランドの萌芽
(1) 企業ブランドによるサービス・ブランドの代替
A社とT社は,ともに産業廃棄物処理サービスに対してブランドを持っていない。企業ブランド(コーポレイト・ブランド)がそのままサービス・ブランドとして通用している例である。サービスにはブランドがなかなか付けられないのが普通で,産業向けサービスであれば,なおさらのことと考えられる。
(2) 産業廃棄物における価格通念の否定
アンケートの結果からは,処理価格は重視されるものの,業廃棄物処理業者の選定は価格以外の評価項目を加えて総合的な評価によってなされることが分かった。このことは,従来言われてきた産業廃棄物処理業者は価格だけで選択されるという通念を否定するものである。優秀業者としての評価が高いA社とT社の評価を見ても,価格の評価は低い(図 32,図 33)。
図 32 A社の評価
価格は,コスト・パフォーマンスを測る尺度になり得る。その場合,コストと比較すべきパフォーマンスを代表するのがブランドである。また一方,ブランドと複合した価格情報は,品質推定機能を提供することがある。いずれについても,コスト・パフォーマンスの評価を行うのは,買い手である。
以上のことから,産業廃棄物処理分野における高価値ブランド業者にも,価格が高いにも関わらず選ばれていることは,価格の品質推定機能が働いていることによると考えられる。A社とT社が,価格が高くても選ばれていることは,ブランド力と需給曲線で説明できる。ブランド力と価格についての上原(1999)の説明を要約すれば,次の通りである(注[80])。まず,ブランドは品質情報の集約であり,製品にブランドが賦与されると買い手はブランドから品質を推定するようになり,価格からの品質推定の比率を減じるという。すなわち,ブランドは価格の品質推定機能を弱め,コスト・パフォーマンス識別機能を強める作業をもっているというのである。このことから,ブランド力が強ければ強いほど,相応に価格を下げると,買い手はコスト・パフォーマンスの高さを強く感じ,需要は大きく増加するのに対し,ブランド力の弱い製品はかなり価格を下げても,買い手のもともとの品質評価が低いため,需要は大きく増えないという。逆に,値上げの場合,ブランド力の強い製品では,「高品質だから」という理由で需要はそれほど減少しないが,ブランド力が弱い場合には,「良くないものが高すぎる」として需要が大きく減少するというように,価格を上げるときと下げる時では需要の価格弾性が異なり,その異なり方はブランド力の強い者と弱いものとで逆パターンになると説明している。以上の説明から,名声が高い,即ち高価値ブランドであれば,価格が高くても,あるいは高いと感じても,購入しても良いと判断されるということがわかるのである。
ブランド力が強い者は価格維持戦略をとり,弱い者は価格競争戦略をとらざるを得ない。それゆえに,強いブランドは高収益に結びつく。早期に高価値ブランドを確立した産業廃棄物処理業者は,今後優位な事業展開ができるであろうことが予測できる。
(3) 大資本に対する優位性
アンケートで浮かび上がってきた高価値ブランド業者リストの中には,セメントや鉄鋼のような新たに参入してきた大資本が入っていない。このことは,既存の産業廃棄物処理業者はブランド力の点で他業種からの参入業者に優るということであり,ブランドが既存の産業廃棄物処理業者にとって新規参入の脅威に対抗する有力な手段となり得ることを示唆する。
なぜ新規参入大資本がブランド上位に入らないのかを考える。第1の仮定は,セメントや鉄鋼製造業者は,産業廃棄物処理業者としては優秀だと認識されていないことである。第2の仮定は,それらは産業廃棄物処理業者とは認識されていないことである。そして,第3の仮定は,ブランドを作るのは文化や歴史であり,セメントや鉄鋼製造業者が産廃ブランドとして成長するにはまだ時間が必要であることである。以上3つの仮定を列挙したが,第1節で論じたことと併せて考察すれば,第3の仮定が最も蓋然性が高いと言えるだろう。産業廃棄物処理サービス分野におけるブランド形成の仕組みは,図 31に示した通りであり,これに沿って適切なブランド戦略を展開すれば,遅かれ早かれ強力な産廃ブランドとして台頭してくる可能性が考えられるだろう。
ともあれ,現段階では既存の産業廃棄物処理業者がヨリ強力なブランド力を保持しているのである。
3 競争戦略としてのブランド
(1) 産業化社会の終焉
上原(1999)は,これまで日本の消費者は企業のオファーに生活の豊かさを見出してきたが,こうした産業化社会が終わる,すなわち勤労社会から生活社会に変化しつつあると述べている(注[81])。このような社会構造・産業構造の変化を,企業の市場行動モードの変化に着目して嶋口(1995)は,enactmentからfitness,そしてinteractionへの変化であると解釈している(注[82])。斯かる状況にあっては,生活者はもはや企業が届けてくるものをそのまま受容することはなく,生活者がモノヅクリの過程にまで干渉する,あるいは評価することになる。その動きの例が,原材料の表示,産地ブランド,トレーサビリティへの関心の高まりなどである。この現象を産業財にまで延長して考えれば,工業製品であってもいずれは部品や原材料の由来を表示することが重要になるはずである。第1節で言及した「産業財における顧客の顧客戦略」が重要になる。
そうした流れを正しく活用すれば,生産過程で生じた廃棄物(バッズ)にまで生活者の関心を向けることになる。生産財の全て(原材料;建物・工場設備;用務・産業サービス)について顧客の関心が向かうとなれば,産業廃棄物処理も顧客に対して「自慢できる」ものでなければならない。その時,産業廃棄物ブランドがパワーを発揮することになる。
従来,積極的に探索されないサービスである産業廃棄物処理サービスは,顧客のプライバシーを守り,顧客企業が廃棄物を発生していることを世間にイメージさせてはならなかった。そのため,産業廃棄物処理業者はあまり世間の表に出ないことが美徳とされ,そうした産業廃棄物処理業者が顧客から信頼されるものと考えられてきた。しかし,産業化社会の終焉とともに,従来の日陰にあるべき産業廃棄物処理という抑制はなくなり,むしろ積極的に世間に出る,目立つ産廃ブランドとした者が競争に打ち勝つことになるだろう。
(2) 企業における意思決定の迅速化
余田ら(2006)によると,経済成長率が鈍化し,競争が激化してきている状況では,企業は迅速な経営判断・意思決定が求められており,そのため企業の現場では,権限委譲・現場裁量を進めているという(注[83])。中央集権的に購買を行っている場合には,「買い叩きの専門部門」たる購買担当者が産業廃棄物処理業者の選定も行ってきた。しかし,現場裁量で産業廃棄物処理サービスの購入を決定するようになると,現場の技術者の影響力が強くなる。産業廃棄物は現場の人間にとって,より切実な問題である。たとえば「作業環境をよくしたい」,「誇れる製品を作るために環境対策をきちんとしたい」などは,現場の人間の発想である。
技術部門は,産業財ブランドの価値を認める傾向にあることは明らかにされている(注[84])。一方,産業財購買の意思決定においては,関係者の意思決定への関与度および知識水準が,主観的判断依存度と反比例の関係にあることが明らかになっている(注[85])。このことは,本研究のアンケートの結果と合致する。
また,アンケートの結果では,互いに異なる価値観と判断基準を持った人々が,産業廃棄物処理業者の選定に関わっており,それぞれの人が異なる判断を下しながらも,組織としての決定を下していることが分かった。組織としての判断は,突き詰めて行けば個人の意思の集合ということになる。そして,個人の意思は,個人の知識と個人の立場から形成されるであろう。
産業廃棄物処理を含む産業財取引に係る判断は,客観的データや基準に基づく「認知的処理」に拠るが,合理的とは言えない主観的処理,「感情的処理」が入り込む余地がある。個人の意思決定の場合は,とりわけ感情的処理の占める部分が大きいが,それらが集合して組織の意思になる過程を経て,非合理的な部分は取り除かれて組織としての合理性の高い意思が形成される。組織購買のメカニズムについては,Websterら(1972)(注[86])の,あるいはSheth(1973)(注[87])の購買センターの概念(図 34および図 35)で説明される。
図 34 組織の購買意思決定モデル (Webster and Wind, 1972)(注[88])
図 35 産業需要家の行動モデル (Sheth, 1973)(注[89])
Websterらのモデルでは,購買意思決定に影響する要因を外的環境に係るものと,購買組織の性格や能力に係るものの2層からなるとし,それらが購買センター組織に作用することで,集団および個人の意思決定を促して組織の購買意思決定に至るものとしている。Shethのモデルは,組織としての産業需要家が,サプライヤーもしくはブランドを選択するプロセスに関与する種々の要因について,その相互関係を記述している。これら購買センターモデルは,互いに矛盾するものでなく,また共通して購買センターを構成する個人の意思の役割を重視している。
購買センターを構成する個人の情報処理については,Bettman (1979)(注[90])による「消費者の情報処理理論」がよく説明している(図 36)。Bettmanの理論によれば,外部から人間の脳に入力した情報は,いったん整理されて長期記憶化し,次に新しい情報が入力したときに永久記憶メモリから引き出され新しい情報と突き合わされて,購買の意思決定がなされる。組織に長期記憶のメカニズムはないが,組織を構成する個人には長期記憶のメカニズムが備わり,組織の意思決定に大きな影響を及ぼす。個人の脳内で長期記憶化するには,整理されて引き出しやすい形で記憶に収納される必要があるので,ブランドは重要である。なぜならば,ブランドは記憶においてインデックスの役割をするからである。
図 36 消費者の記憶・意思決定モデル(Bettman, 1979)(注[91])
以上の通り,アンケートの結果と,組織の購買意思決定のメカニズム理論を突き合わせて検討すれば,産業廃棄物処理サービスのセールスにおいて取るべき有効な戦略として,次のような手順が導かれる。
- まず,マス広告その他の手段を用いて相手購買センター構成員(現場の技術者も含まれる)まで自社の情報を届けておく。その際,長期記憶化することを意識してブランドを有効に活用する。
- その上で,ブランドを武器として購買センター構成員に人的な接触をする。
- 各個人に対して,その地位・権限や,知識レベルに応じた情報を提供する。
(3) 産業廃棄物処理マーケティングにおける情報の重要性
産業財マーケティングでは,コンセプト提案力の強い者が勝利すると言われている。一方で,産業財マーケティングでは情報格差を創出しづらく差別化が困難であると言われるが,その反面,産業廃棄物処理マーケティングでは事業者に情報がよく伝わっていないと言われる。後の言説が正しいとすれば,情報量において産業廃棄物処理業者は事業者よりも有利な立場にあることになり,差別化もできるであろうし,強力なコンセプト提案もできるはずである。
アンケートの結果によれば,A社とT社は,買い手と同業者の両方から支持を受けている(表 20)。このことは,買い手と売り手との間で共有される価値基準があることと解釈できるだろう。産業廃棄物処理業者と事業者のそれぞれの価値基準は,完全には一致しないにしても,まったく別の方向を志向するものではないということである。もし買い手と売り手の間に差があるとすれば,それは情報量の多寡であって価値基準の差ではないだろう(図 32,図 33)。この推論が正しいとすれば,現在の産業廃棄物処理市場は,マーケティング力のある産業廃棄物処理業者にとって最も有利な状況である筈である。すなわち,産業廃棄物処理業者は,産業廃棄物処理サービスの理想について自身が考えるベンチマークがあれば,それに沿って差別化商品を作り出し,積極的に情報発信をすれば良いのである。
消費とは,物質的消費と意味的消費の合成であり,このことは消費財についてばかりでなく産業廃棄物処理サービスにも適用されるべきことを述べた。余田 (2006) は,品質の本質を分析して,「機能上の品質」とそれに基づく「知覚品質」があるとし,強いブランドではその相対的な知覚品質の高さが高収益に結びつくとしている(注[92])。すなわち,機能上の品質を向上しても,知覚品質に結びつかなければ収益に影響しない。ここで言う知覚品質とは,情報そのものである。機能上の品質と知覚品質の結びつきの強さは,産業財と消費財で異なるであろうし,産業財の中でも商品カテゴリーごとに異なるであろう。産業廃棄物処理サービスでは,図 9で言うところのコア便益の差別化が難しく,それゆえに,コア便益から外縁方向に向かった拡張サービス,あるいは潜在サービスのレベルでの差別化に頼ることになるだろう。なお,図 9のモデルでは,外に向かうほど商品の実体的要素が減じて情報的要素が増加する。アンケートでは,事業者関係者が産業廃棄物処理業者を評価している項目を因子分析して,(1)マーケティング能力,(2)具体的業務処理能力,そして(3)技術対応能力の3因子を特定した。これら評価因子のうち,マーケティング能力とは,情報そのものである。
以上のことをまとめて,産業廃棄物処理マーケティングにおける情報的要素の重要性を認識すべきことを強調する。産業廃棄物処理施設を設置することだけではなく,施設を設置したことを市場の知覚品質に結びつけることや,施設が環境負荷の小さい処理を達成していることを顧客の知覚品質に結びつけることがヨリ重要である。そのことを認識し,知覚品質を構成する要素を整理すれば,やはり図 31の構造に帰着し,改めてブランドの重要性を強調するに至るのである。
(4) 協働型マーケティング
勤労社会が勢いを失って生活社会に転換して行くと,協働型マーケティングが台頭することを上原(1999)は主張している(注[93])。現実の消費財マーケティングの状況を見ると,すでに協働型マーケティングが伸長してきている例が多く見られる。実は,産業財分野では昔から協働型マーケティングが展開されてきた。産業財分野では,財貨の設計から供給までが,需要家とサプライヤーの間の協同作業に負うところが大きかった。それが,下請け構造や系列構造を生み出してきたという側面もある(注[94])。このような産業財分野でも,前述の現場裁量拡大などの流れから,すでに「買い叩く」が「開発購買」に転換してきているという(注[95])。
また,サービス財は,買い手と売り手の協働によって価値が生み出されることはすでに説明され尽くしている。物財であれば,サプライヤーの工場で作られた製品を需要家は工場とは別の場所で消費する。すなわち,物財の取引においては,売り手と買い手は時間や空間を共有する必要がないのである。それに対して,サービス財の取引は,売り手と買い手が時間と空間を共有し,そこで価値が生み出される。学校で提供される教育サービスがそうであるし,産業財ではビル清掃やエレベーター保守サービスなどが該当する。以上の知識を基本的な視点として産業廃棄物処理サービスのこれまでの流れを俯瞰する。
環境規制が無いか緩かった時代には,産業廃棄物処理業は顧客の目の前から廃棄物を除去するという,産業廃棄物処理のコア効用だけを提供すれば良かった。嶋口の言うenactmentの時代である。
法律が厳しくなり,また増大する産業廃棄物に処理施設が追いつかないなど産業廃棄物処理を取り巻く環境も更に厳しくなった。そして,産業廃棄物が多様化し顧客のニーズも多様化の度合いを強めると,産業廃棄物処理業者はそれらに応える形で定期的なルート収集,規格化された保管容器の配置,最終処分場の見学や案内など,顧客の満足度を高めるために様々なことをするようになった。上原が言う操作型マーケティングであり,嶋口の市場行動モード分類ではfitnessである。
2010年代初頭の現在,わが国の産業廃棄物処理業界は,この操作型マーケティングあるいはfitnessの最終段階にあるものと考えられる。なぜならば,もはや産業廃棄物の排出量の伸びは見込めなくなり,これまでのような大量消費・大量排出・大量処理という産業廃棄物処理事業の構造が成り立たなくなる。そのことを裏付けるのが,産廃ブランド調査で明らかになった産業廃棄物処理業者の評価因子(表 19)である。産業廃棄物処理業者を評価する基準が,大量の産業廃棄物を処理するのに必要なハードウェアから,情報的側面を中心とするマーケティング能力が重視されるようになっていることが覗われるのである。単純に適正な処理の遂行であれば,図 9の基本的サービスにあたるだろうが,現在の状況は,顧客に対して若干の優越的満足を与える期待サービス~拡張サービスのレベルでの競争が行われるようになってきているのではないかと考えられるのである。
さて,情報社会化・生活社会化が更に進展した時の状態を上原は協働型マーケティングと規定し,嶋口はinteractionと説明している。その時,産業廃棄物処理マーケティングと産業廃棄物ブランドはどうなるのだろうか。産業廃棄物処理サービスの物理的効用あるいはコア効用は単純なので,そこを差別化することは困難である。このことは,産業廃棄物処理業者から事業者への提案にも限界があるということである。そうなると,協働型マーケティングが注目されるようになり,産業廃棄物処理の分野でも協働型マーケティングが広がることになる。そして産業廃棄物処理業者間の競争の場は,図 9の拡張サービス~潜在サービスに完全に移行するだろう。ここまでが,産業廃棄物処理マーケティングのシナリオである。
協働型マーケティングは,事業者と産業廃棄物処理業者が最善の産業廃棄物処理システムを構築するために協力することを前提としている。この協働型マーケティングが従来の提案型・操作型のマーケティングと大きく異なるのは,事前にオファーが見えないことである。提案型・操作型のマーケティングであれば,取引の前に売り手は既に提案を用意していて,それを売り込めば良い。物財であれば,製品サンプルを持って行けば良い。しかし,サービス財の協働型マーケティングでは,取引前に売り手から買い手にアピールするものがなく,買い手がサプライヤーを探す手がかりとしてのブランドは益々重要になるはずである。
脚注
(注[69])Kotler, P., Marketing Management: 11th edition, international edition, Prentice Hall Edition, 2003, pp. 418-424.
(注[70])物理的効用と意味的効用の概念は,大友純「マーケティング・コミュニケーションの戦略課題とその本質-プロモーション戦略の求心的要因を求めて-」『明大商学論叢』,83巻1号,2001年,205-213ページに詳しい。
(注[71])余田拓郎,首藤明敏『B2Bブランディング – 企業間の取引接点を強化する』,日本経済新聞社,2006年,30-31ページ。
(注[72])Kotler, P., Marketing Management: 11th edition, international edition, Prentice Hall Edition, 2003, pp.411-412.
(注[73])Kotlerの前掲書412ページから,MRO財の購買に関する記述を引用する。
MRO財は,通常は最小の探索コストで反復購入される。また,単価が低い一方で多くの顧客が地理的に分散している場合には,仲買業者を経由して販売されるのが普通である。供給者にあまり差がなく,ブランド選好が強くないので,価格とサービスが重視される。企業向けサービスには,維持・補修サービス(窓清掃,コピー機修理など)および,経営顧問サービス(法務,経営管理)が含まれる。維持・補修サービスは,契約の下で小規模業者によって提供される。また,当該機器の製造元によってもサービスを受けられる。経営顧問サービスは,業者の評判やそのスタッフに対する評価をもとに選択される。(筆者訳)
(注[74])余田拓郎,首藤明敏『B2Bブランディング – 企業間の取引接点を強化する』,日本経済新聞社,2006年,19-21ページ。
片平秀貴『新版パワー・ブランドの本質』,ダイヤモンド社,1999年,2-10ページ。
(注[75])余田らの前掲書40ページから,インテル社のブランド戦略の記述を引用する。
インテルは,自社の特許技術を守るために裁判に打って出る戦略から,自社のブランドを守る戦略にシフトしている。最初から囲い込んでしまうと市場が拡がらないので,クロスライセンスで技術供与したり,一部をオープンにしたりして他のプレーヤーの参画を促しながら市場を拡大させる一方,商標をとることでシェアと先行者利益を獲得しようとしている。
(注[76])崔容薰「産業財ブランド研究の視座」『季刊マーケティングジャーナル』,25号,2008年,59-81ページ。
(注[77])崔のライクラのブランドへの取組に関する記述を引用する。
オペロンテックス社は,『ライクラ®』でブランドに関して直の顧客だけにとどまらず,アパレル小売り,消費者に至るまでの全方位に渡るブランド及びマーケティング活動を進めている。その目的は,サプライチェーンを構成するすべてのメンバーに『ライクラ®』ブランドの機能面でのベネフィットと,それを身につけることによって得られる「楽しさ」,「美しさ」,「自信」といった情緒面でのベネフィットをアピールし,選好を獲得することにある。それによって,直の顧客との取引においては競合他社との価格競争を回避し,プレミアム価格を獲得できる有利なポジションを先占すること,「顧客の顧客」に対してはファッショナブルで高品質なブランド・イメージを植えつけることで,『ライクラ®』繊維の成分として含有する最終製品の購買に革新を与えることをねらっている。
(注[78])Kotler, P., Marketing Management: 11th edition, international edition, Prentice Hall Edition, 2003, p. 481.
(注[79])上原征彦『マーケティング戦略論』,有斐閣,1999年,68ページ,140ページ。
(注[80])上原征彦『マーケティング戦略論』,有斐閣,1999年,148-150。
(注[81])上原征彦『マーケティング戦略論』,有斐閣,1999年,7-15ページ。
(注[82])嶋口充輝「関係性時代のインタラクティブ・マーケティング」『季刊マーケティングジャーナル』,15巻1号, 1995年,6-16ページから,嶋口が提示している企業の市場行動モードの3類型を次に要約する。
第1のマーケティング・パラダイムであるenactmentパラダイム(おしきせ型:筆者)では,売り手が自らの信ずる提供価値を買い手に一方的に推奨・説得して行く。第2のfitnessパラダイム(ニーズ適応型:筆者)では,継続取引のために,買い手の価値から出発し,その価値の調査や分析によって探索・発見し,そこで明らかにされた価値をマーケット・インという形で組織の事業の商品コンセプトに置き換え,マーケティング・ミックスとして価値の政策セットに仕立てて売り手に再びプロダクト・アウトしていくというプロセスをとる。第3のinteractionパラダイム(相互交渉型:筆者)の下では,価値やニーズの読めなくなった買い手と価値を提供しようとする売り手とは,取引者としてより取組者同士として一体化し,強い信頼関係と絆を結びながら,パートナーとして新しい価値を継続的に共創して行こうとする。
(注[83])余田拓郎,首藤明敏『B2Bブランディング – 企業間の取引接点を強化する』,日本経済新聞社,2006年,22-24ページ。
(注[84])崔容薰「産業財ブランド研究の視座」『季刊マーケティングジャーナル』25号,2008年,59-81ページでは,技術部門のブランドに対する態度を次のように記述している。
購買センターに関わるメンバーの中で,技術者が有名ブランドに対して26%の価値プレミアムを払う用意があり,また,ユーザーと技術者がブランド名に高い重要度を付与したことを確認した。特に技術的専門性の高い製品分野では購買部門より技術部門の人間が意思決定に強い影響力を持つという既存の知見を考えると,ブランド活動のターゲットとして誰を対象にすべきかに対するインプリケーションが得られる。
(注[86])Webster, E. F. Jr. and Y. Wind, “A General Model for Understanding Organizational Buying Behavior” in Journal of Marketing, vol. 36 (1972), pp. 12-19.
(注[87])Sheth, J. N., “A Model of Industrial Buyer” in Journal of Marketing, vol. 37 (1973), pp. 50-56.
(注[88])図 34のオリジナルは,Websteらの論文15ページに,“A model of organizational buying behavior”として掲載されている。
(注[89])図 35のオリジナルは,Shethの論文51ページに,“An integrated model of industrial buyer behavior”として掲載されている。
(注[90])Bettman, R. J., An Information Processing Theory of Consumer Choice, Addison-Wesley Publishing Company, 1979.
(注[91])図 36のオリジナルは,Bettmanの前掲書140ページに,人間の記憶システムにおける情報フローを説明する図として掲載されている。
(注[92])余田拓郎,首藤明敏『B2Bブランディング – 企業間の取引接点を強化する』,日本経済新聞社,2006年,35ページから,知覚品質に関する余田らの記述を次に引用する。
強いブランドの相対的な「知覚品質」の高さが収益に結びつく。一般的に品質とは,客観的で測定可能な「機能上の品質」のことを指す。一方,知覚品質とは,顧客が認識する「品質や機能の印象」ことである。この規格品質が高いROIに結びつくことが,多くの実証研究でも立証されている。3000ぐらいの事業分野の企業データを分析したPIMSの研究においても,いろいろな経営要素があるなかで,知覚品質を高めるとROI,ORSのどちらも高まるという明らかに正の相関にあるという結果がでている。
(注[93])上原征彦『マーケティング戦略論』,有斐閣,1999年,279-291ページから,協働型マーケティングに関する記述を要約する。
生活が物質的に充足し,生活者は物資を超えた生活の質を希求するようになった。そのことに伴って,生活者は,企業が提供する財貨を買うために働くことよりも,生活の豊かさの創造を重視するようになってきている。これは,生活者が企業のオファーへの依存度を弱め,企業にとっては生活者の情報を把握することを困難にすることである。そこで,従来の操作型マーケティングに代わるパラダイム,企業が生活者と一緒に製品を創造して行く協働型マーケティングが注目されるようになる。
(注[94])下請け構造や系列構造は,売り手と買い手が情報を共有して安定的な関係を構築することで,効率的な資源配分がなされ長期的な投資が可能になるという側面を評価すべきである。系列とは,資本や人事交流,あるいは取引期間の長さなどにより,特別に密接な関係にある企業群のことであり,下請とは法律が定義する経営規模の中小企業がヨリ大規模な親企業から受注している状態を言う。こうした系列取引や下請構造が形成された本来の背景・目的は,親企業が下請企業等の専門的能力を評価してアウトソーシングすることである。親企業は,下請企業に対して資金面,技術面での支援を行ってきていることが多いという(財団法人中小企業調査協会『下請系列構造調査報告書』,1977年)。また,親企業が大規模な事業変更をする場合には,下請企業に対しても特別な転換支援をする例が多い。このような支援は,系列企業間の単純なファミリー意識によってなされるのではなく,経済合理性に根ざすものである。高度な業務をアウトソーシングするに際して,委託元は委託先に対して投資をすることになるが,投資の効率を考慮すれば,長期にわたる安定的な関係を維持することが,委託元と委託先の双方にとって最適解となる場合がある。
(注[95])余田拓郎『カスタマー・リレーションの戦略論理—産業財マーケティング再考』,白桃書房,2000年,178-182ページ。

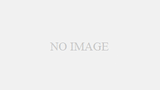
コメント