第6章 理論の拡張
1 オープン市場の必要性の再検討
優良な産業廃棄物処理業者を育成し,不法投棄・不適正処理を抑制するために,国は「優良産廃処理業者認定制度」を推進している。この制度は,インターネットでの情報開示を主とする5つの要件を満たし優良産廃処理業者と認定される者に対して,業の許可期限の延長などの優遇を与える。換言すれば,インターネットによる情報開示を促進し,需要家に産業廃棄物処理業者選択の機会を増やす政策である。このことは,第3章に述べたとおりである。制度が依拠しているのは,産業廃棄物処理がオープンな市場で取引されるようになれば,優良業者にとっての機会が増えるという理論である。
ここで,第2章で設定したのと同様に,オープンな市場とは,(1)参入がオープンであること,(2)需要家がサプライヤーを容易に探索できること,そして(3)サプライヤーが需要家と容易に関係を構築できることの3条件を同時に満たすものとしよう。そのような市場にあっては,1つの商品カテゴリーにおいても多様な商品が供給されるだろう。また,そこでは,複数の商品のコスト・パフォーマンスの比較が可能であり,その結果,コスト・パフォーマンスが最も高い商品が選択されるようになる。またそのことが,イノベーションを促し,コスト・パフォーマンスがヨリ高い製品の市場への供給をもたらす。そして,高コスト・パフォーマンス商品は,更なる需要の拡大をもたらすだろう。
しかしながら,オープン市場が以上のような機能を発揮するのは,あくまでも3条件すべてを満たす場合だけであって,それらのいずれかが欠けても期待するような機能を発揮し得ない。優良産廃処理業者認定制度は,事業者が産業廃棄物処理業者を探索する機能は提供するものの,それ以外の条件を満たしていない。法律は,プロセス規制中心であるうえに委託契約関係の事項等を細かく規制しており,業者の参入や新規テクノロジー,新規ビジネスモデルの導入を阻害している。また,産業廃棄物の発生量はすでに減少局面に入っており,需要拡大が望めない市場オープン化に意味があるのかという疑問を抱かざるを得ない。
優良産廃処理業者認定制度は,事業者による産業廃棄物処理業者の探索を支援すれば,自ずと優良な産業廃棄物処理業者が選択されるようになるという前提のもとで実施されていることが分かる。しかし,アンケートで明らかになったことは,優良な産業廃棄物処理業者への委託を阻んでいるのは,産業廃棄物処理業者を検索できないことではないし,価格でも処理パフォーマンスでもなく,系列取引など事業者自身の社内事情なのである(表 26)。この阻害要因を取り除くことこそ,産業廃棄物処理業の優良化を実現するカギとなるはずである。
今後本格化するであろう協働化マーケティングの時代において,オープン市場がどのように働くかを整理しなければならない。オープンな市場とは,比較して最良のものが選べるような交換の場のことである。オープンな市場で選択の基準となるのは,コスト・パフォーマンスである。それを構成するパラメーターは価格と意味的効用であるが,そのうちの意味的効用は,産業廃棄物処理というサービス財,それも地域コミュニティに対する配慮を要するという複雑な財貨に対しては,事前の評価が困難なため,品質の総合的評価であるブランドで代替されることになるだろう。
オープンな市場があってもなくても,産業廃棄物処理業者が生き残るためには,情報を操作して差別化を図らなければならない。オープンな市場が主たる交換の場となった場合,他の要素で優秀な産業廃棄物処理業者も,情報の操作が上手くできなければ価格でしか評価されないことになる。オープンな市場は,産業廃棄物取引の流動化をもたらすであろうが,その中で組織取引を確立できる産業廃棄物処理業者こそが優良な処理業者ということになるだろう。
表 26 優秀処理業者に委託しない理由
| 回答率 | 回答数 | |
| 価格が折り合わない | 18% | 16 |
| 系列取引の問題がある | 19% | 17 |
| 自社の必要とする技術を持っていない | 6% | 5 |
| 自社の必要とする許可を持っていない | 3% | 3 |
| 社内の調整の問題 | 41% | 37 |
| その他 | 29% | 26 |
2 環境ビジネスとブランド
(1) 社会に対するブランドの役割
第3章で論じたように,産業廃棄物処理業の経営に特異的なこととして,処理施設の確保の困難さがある。産業廃棄物処理施設の設置難が,マクロ視点での産業廃棄物処理の阻害要因のひとつとなっていることは述べたとおりである。施設設置難の中で,施設の設置に成功した産業廃棄物処理業者は営業上の強い立場を確保できる。
産業廃棄物処理施設の設置を困難にしているのは,住民の同意である。産業廃棄物処理施設は, NIMBY (Not In My Backyard),あるいはLULU (Locally Unpleasant (Unwanted) Land Use)などと言われる。つまり,社会的に必要な施設であることを理解しているが,いざ自分の生活の近いところに設置されるとなると,嫌悪することになるというものである。基本的に,周辺に住む人々はそうした施設の設置になかなか同意を与えない。このことが各地に紛争を引き起こしている。産業廃棄物処理施設のうちでも,埋立処分場の設置は特に困難である。埋立は空間を消費して行く,いわば消耗品である。産業廃棄物処理業者は,現在埋立処分施設を稼働させていても,常に次の処分場のことを考えていなければならない。
産業廃棄物処理施設を設置する際に,処分業者は住民との関係構築に注力するが,そこでブランドが重要な役を演ずるであろうことは容易に想像がつく。基本的に住民は産業廃棄物処理施設の設置に反対である。反対意識を補償するために,まず産業廃棄物処理業者は雇用やその他の地元利益を提案する。その上で産業廃棄物処理業者と住民との接触と交渉があり,最終的な合意形成がなされる(なされない)。ここで住民が産業廃棄物処理施設設置の可否を判断する材料は,(1)環境影響などの技術的要素,(2)産業廃棄物に対する認識や,(3)当該産業廃棄物処理業者の評判,などである。これらの判断要素を見て気付くことは,それらが消費財よりもむしろ産業財の購買における評価要素と近いことである。
消費者や産業需要家が財貨を購買する過程を時間軸に沿って表したものが図 37である。買い手は,財貨を購入する前と後に財貨の評価を行う。消費財の購入と産業財のそれとで,最も異なるのが,事前評価の重みである。産業需要家が産業財を購入する際には,事前評価を特に念入りにする。先ず,物理的性能の予測を行う。すなわち,財貨の性能や価格を念入りに吟味する。次いで,その財貨を購入して得られる結果,意味的性能を予測する。具体的には,それを使用して作る製品の品質・顧客満足度・売上・利益率・従業員の安全その他の影響予測である。物理的性能予測と,意味的性能予測を段階を踏んで実行するのが産業財購入の特徴である。つまり,産業需要家は,物理的性能を調べることで購入すべき財貨を絞り込み,その次に,財貨の属性の他にサプライヤーの能力などを含めて更に詳しく吟味して,意味的性能の予測に至るのである。消費財の場合には,事前評価は比較的簡単で,物理的性能予測と意味的性能予測の段階を踏まないことや,物理的性能予測をしないことすらある。
産業廃棄物処理施設の設置に対する同意という問題を処理する地域住民は,まず物理的性能予測,次いで意味的性能予測を段階を踏んで実施している。最初に,地域住民は,産業廃棄物処理施設の環境パフォーマンスや,法律要件への適合状況を調べて,その施設の物理的性能を知る。普通は,この段階で不同意となることは,まずない。もしこの段階で疑義が生じた場合でも,資料を調べたり産業廃棄物処理業者と交渉したりすることで,大部分は解決する。その次に地域住民は,地域の環境特性のほかに,産業廃棄物処理業者の評判や,住民同士の利害関係などを含めて,施設設置が実現した場合のイメージ,すなわち意味的性能を予測する。そして,紛争化するのは,だいたい後段の意味的性能予測で良い結果が得られない場合である。
図 37 財貨の購買決定プロセス
ここから,地元との合意形成のプロセスと,産業需要家が財貨の購買を決定するプロセスの類似性が示唆される。つまり,地元住民は,物理的性能評価を基本的な判断の拠り所としながらも,認知的処理から感情的処理をして,産業廃棄物処理施設の設置の可否を決めているという事実である。処理施設の同意問題においては,特に感情的処理の比重が大きいとすれば,やはりブランド力が施設設置に大きな影響を及ぼすということが言えるだろう。
以上のことから,さらに「本来の産業財マーケティングに巧みな産業廃棄物処理業者は,産業廃棄物処理施設の設置にも巧みであり,そのことがその業者の社会的評価を更に高めるという好循環を形成している」という仮定が導かれるだろう。これらのことを図 38に示した。
地域住民にとって,産業廃棄物処理事業や産業廃棄物処理施設は,自らの生活とは直接関係のない迷惑な存在である。つまり,第2章2で触れた非探索品(unsought goods)の極端な例であり,事業主体から地域住民に対して積極的な説明が必要である。買い手である地域住民は,売り手からの説明を受け,投資と価値分配の概要を理解して初めて詳しい検討に入る。一方,産業需要家が産業財を欲するのは,それが自らの事業の生産性につながると確証できる場合に限ることであり,充分な情報がない状態で積極的に欲するものではないのである。
(2) ブランドの対顧客機能から対地域機能への拡張
第2章では,環境ビジネスの地元コミュニティは,産業廃棄物処理業者にとっては,事業者と同列に扱うべき顧客であることを見た。そして,ここまで,産業廃棄物処理業では,ブランドの機能が(1)顧客(事業者)と,(2)地域コミュニティの両方に対して作用することを見てきた。両者は,認知的処理から感情的処理に至ることが共通である。この共通点を軸に考えると,ブランドの対顧客機能と,対地域コミュニティ機能の本質にほとんど差がないことがわかった。
第5章に示した産業廃棄物処理ブランドの構成(図 31)に,地元対策の要素を加えて得られたものが,拡張概念である「産業廃棄物処理業におけるブランドの役割」である(図 39)。ブランドの力を活用して施設設置に成功することが,産業廃棄物処理業者の実績となり,それがフィードバックしてブランドを更に強化し,強化されたブランドがまた地元対策を有利にするという構図である。
図 39 産業廃棄物処理業におけるブランドの役割
ブランドの力の1つが,関係の薄い人からも評価を受けることである。社会に浸透したブランドであれば,直接関係のない第三者でもそれに触れる機会があり,前述Bettmanモデルの長期記憶に入る確率も高い。ブランドにはこの機能があるから,直接の取引相手ではない地域コミュニティに対しても作用する。このことは,施設の設置が特異な要素である産業廃棄物処理業で特に重要であるが,嫌悪施設設置一般についてあてはまるはずである。このブランドの対顧客機能と対地域コミュニティ機能の複合作用は,さらに,施設に限らず地域コミュニティとの関係一般に関するブランドの作用を説明する。たとえば,産業廃棄物処理業者の社員が地元で生活する場合,あるいは地元から社員を採用する場合などの地元の受容の度合いに,ブランドが影響するだろうことである。更に重要なことは,その施設に産業廃棄物を搬入することについてもブランドのパワーが不可欠であることである。
産業廃棄物処理施設の設置に際しては,地縁が大切だと言われる。しかし,上述のことを考えると,地縁とは結局のところ,地域における,あるいは地域に対するブランド力であると考えられる。このことが正しければ,地縁は歴史や伝統に根ざすものではあるけれど,ブランド戦略のもとに操作が可能であるし,地域での活動以外の要素を以て地縁に反映させることも出来るのである。また,第5章では,産業廃棄物処理マーケティングにおける情報の重要性と,協働型マーケティングの予測を主に事業者にあてはめて検討したが,それらはそのまま地元コミュニティに当てはめることができる。
ところで,第2章では,S-Dロジックを用いて産業廃棄物処理の構造と機能を論じ,産業廃棄物処理とは産業廃棄物処理業者・排出事業者・地元住民が共同して環境価値を創出する行為であることを見いだして,図 14を導いた。それと,本節で得た図 38を比較すれば,両者の類似性あるいは近似性に気づかざるを得ない。すなわち,産業廃棄物処理に係るブランド価値も,産業廃棄物処理業者・排出事業者・地元住民が共同して作り出すものであり,それは産業廃棄物処理によって創出される価値の一部なのである。あるいは,産業廃棄物処理によって創出される価値の総合的な評価が,ブランドであると解釈しても良いだろう。
3 環境ビジネスのコスト・パフォーマンス(注[99])
(1) 構造的な排出抑制傾向
産業廃棄物の排出量は80年代に大きく伸びたが,90年代以降ほとんど横ばい状態であることを第1章に述べた。80年代のバブル景気の時代には,増大する産業廃棄物に対して中間処理・リサイクル施設の整備が追いつかず,埋立処分や当時は可能だった海洋投入処分に依存せざるを得なかった(注[100])。産業廃棄物の成長の鈍化はバブル景気の崩壊と時期が重なったため,当初は景気の影響を受けた一時的なものだと思われていた。しかし,その後の状況を見れば,このような推測は外れていたと言えるようである。
産業廃棄物排出量の伸びの鈍化は,事業者の意識と行動の転換によるものと考えるのが妥当である。経済が成長し景気が良い当時は,産業廃棄物の処理費用が未だ安かったこともあり,事業者にとって廃棄物を大量に排出しながら生産に邁進することが経済的に最適解であった。しかし,処理施設の容量不足や処理費用の高騰など,産業廃棄物を排出することを困難にする要因が増えるに従い,コストを掛けてでも廃棄物を減らした方がトータルで見れば経済効率でまさると事業者が認識するようになり,事業者の行動が変化するようになったと考えられる。そうした認識のきっかけは,バブル景気の崩壊,事業者における環境マネジメントシステムISO14000シリーズの導入,あるいは生産技術の見直しなどによると考えられる。
(2) 廃棄物処理を含めた交変系のコスト・パフォーマンス
第2章では,交変系はそこに廃棄物処理系を含めることで完成することを論じた。この交変系の効率は, で評価される。ここで,投入に産業廃棄物処理をはじめとする環境保全策のためのコストを含むことは当然として,産出には環境保全の成果を含むものと理解するべきである。
ここで,事業者が産業廃棄物処理など環境保全策を実施する条件について,状況を単純化するために交変系を構成する1個の取引を取り上げて考える。事業者が産業廃棄物などの環境保全策を実施する動機は,損失を減らし生産性を向上することである。そのことを図 40に示した。廃棄物などの環境負荷は,事業者にとっては損失であり,それを抑制することは生産性の向上につながる。しかし,それを損失と認識するか否か,あるいはどの程度の損失と評価するかは,社会環境および事業者の道徳観による。図 40の状態における生産性は,次の式で表される。
(式 1)
ただし,各変数が表す意味は次の通りである。
生産性 P
産出 Y
投入 I
損失 L
付加価値 A
ここに環境保全策を講じた状態は,図 41であり,その状態における生産性は次の式で表される。
(式 2)
ただし,dIは環境保全のための投入の増分,dLは環境保全策の実施による環境負荷の改善分である。環境保全策は,生産性を向上するために行われるのであるから,式3が成り立たなければならない。
(式 3)
式3に式1と式2を代入して,式4が導かれる。
(式 4)
式4は次のとおり整理できる。
(式 5)
であるから,式5から式6が得られる。
(式 6)
式6が説明しているのは,環境保全のための投入に対する環境保全効果の比が を下回るようであれば,そのような環境保全策は実施され得ないということである。1990年以降の産業廃棄物の排出抑制をもたらした要因としてまず考えられるのは,社会環境もしくは事業者の道徳観あるいは価値基準が変化して,産業廃棄物の排出をヨリ大きな損失と認識されるようになったことである。式1では,Lが大きくなり,その結果Pが小さくなった状態である。次いで考えられるのは,投入に比べて効果の大きい産業廃棄物抑制技術が出現したか,そのような社会的状況が到来したかである。
事業者が産業廃棄物処理などの環境保全策を講じる条件は,図 40,図 41,そして式6に示した通りである。産業廃棄物処理業者が事業者から受託するには,これらの条件を満たした上で,事業者自身による自家処理を上回る生産性の高い処理を提供しなければならない。産業廃棄物処理において高い生産性を達成するためには,まず技術面での近代化・高度化を考えるところであるが,施設・設備の近代化・高度化・大規模化は,市場が縮小する現在かなりの困難を伴う。また特に,事業者が新しい産業廃棄物処理委託をする条件は,式6に示されるが,発生抑制を達成して既にPの値が高くなっている現状にあっては,よほど生産性が高い処理でなければ採用されない。
ここまで見てきたように,産業廃棄物処理業の盛衰には事業者の道徳観(価値基準)と社会環境が大きく影響すると考えられるが,この2つの要素に対して影響力が大きいのは規制制度をはじめとする国家の政策である。事業者に環境負荷による損失の大きさを認識させるのは,法律による基準値や罰則であるし,規制制度が処理施設の設置を促進したり阻害したりしている。
図 40 生産の状態
4 今後の産業廃棄物処理業の展開の方向
(1) 売れるブランドこそ最良であること
ブランドとは品質情報の集約であると言われる。これに加えて,社会的評価の集約でもあることを強調したい。本書においてたびたび引用してきたが,Kotler (2003)は,ブランドは,財貨の属性・効用・価値・文化的背景・人格・ユーザーなど多面的な側面を表すとしている(注[101])。また,余田ら(2006)によれば,産業財であっても,「機能上の品質」と並んで「知覚品質」が強いブランドを産み出し,強い収益力をもたらすという(注[102])。そして,本研究では,産業廃棄物処理サービスのブランドが形成されるメカニズムについて,(1)産業廃棄物処理サービスの物理的性能と,(2)産業廃棄物処理業者の情報的サービス,及び(3)事業者による評価,並びに(4)地域コミュニティによる評価の関係を見い出した(図 39)。以上の言説は,互いに矛盾するものではない。いずれも,ブランドとは多様な価値基準による多面的な側面からの評価が集積されたものであることを述べている。それらをまとめると,マーケティングの目的は財貨の価値を高めることであり,ブランドとは財貨の総合的な評価であるという,上原(1999)の言説(注[103])に集約されることになる。
つまるところ,ブランドとは,非常に多くの情報を集約した商品の総合評価であるといえる。となると,結局は,「売れているブランドが良いブランドだ」との一般的言説に辿り着く。「売れている」ということは,「支持されている」ということだからである。一般の商品において,各企業がシェアを広告するのは納得できる。産業廃棄物処理についても,このことは肯んじられるはずである。
ただし,現状ではどの産業廃棄物処理業者が売れているのかを正確に知る機会は少ない。バッズ取引である産業廃棄物処理サービスでは,コスト・パフォーマンス評価が不適切になることがあるので,そこを押さえた上でシェアを情報公開すれば,他の規制は不要になると考えられる。アンケートで分かった事業者の処理業者選択行動と,処理業者の価値判断などからして,事業者にも処理業者にも,そうした政策を受容する条件は整っているといえる。処理業者は自らのシェアを積極的にアピールして行けば良い。
(2) 産業廃棄物処理業の構造とブランドの役割
ここまで論じて来たことをいったん整理して,その上で今後の産業廃棄物処理業の構造変化の方向を検討してみたい。まず,ここまで論じてきた4点の事項を要約することとする。
第1は,産業廃棄物処理は,交変系の中の要素として理解すべきことである(第2章)。産業廃棄物は,天然資源採取から製品の配達までの交変系のあらゆる段階で発生している。それら産業廃棄物は,それが発生した各段階で処理されており,産業廃棄物処理は,生産の一部として機能している。そのため,動脈・静脈あるいは川上・川下のように,生産と対立する存在であるかのような理解は適切でない。
第2は,産業廃棄物処理をはじめとする環境ビジネスが生み出した価値の分配は,売り手と買い手の他に地元コミュニティを加えた3者でなされることである(第2章)。産業廃棄物処理等以外の取引においては,そこで生み出される価値は,売り手と買い手の2者で分配される。すなわち,売り手には,利潤が分配され,買い手にはそれ以外の価値が分配される。しかし,産業廃棄物処理等の環境ビジネスが生み出す主な価値は,生活環境や自然環境の保全であり,それらは主に事業者や産業廃棄物処理施設の地元コミュニティが享受するものである。
第3は,産業廃棄物処理業においてもブランドが重要な役割を果たしていることである(第4章,第5章)。これまでの通念として,産業廃棄物処理サービスの買い手である事業者は,処理業者を選択する際に価格以外に関心がなく,処理業者のブランドは機能しないと考えられてきた。しかし,アンケート調査の結果,産業廃棄物処理に関しても,買い手は産業廃棄物処理業者のブランドを認識した上で,その業者が提供する産業廃棄物処理の性能とコスト・パフォーマンスを吟味していることがわかった。ただし,すべての事業者と産業廃棄物処理業者がこうしたブランドを介した関係を構築しているわけではない。
そして第4は,国が政策として「優良産廃処理業者認定制度」をすすめていることである(第3章)。インターネット上で必要な情報開示を行っている産業廃棄物処理業者を優良業者として認定する制度は,事業者が産業廃棄物処理業者を選び易くすることで,産業廃棄物処理業者の資質を向上するものとされている。情報開示以外に,優良業者としての具体的な要件は定義されておらず,今後どのような産業廃棄物処理業者が選択されることになるかは予測できない。
以上のうち,第1~第3の事項からは,産業廃棄物処理業者と,それと密接な関係にある事業者(産業廃棄物処理業者から見れば得意顧客),そして地元コミュニティの3者が強固な関係を築いている例が既に存在していると考えられる。この3者の関係性は,産業廃棄物処理事業のブランド価値を作り出し,つねに再生産している。産業廃棄物処理業者のブランドが市場に浸透すれば,それまで産業廃棄物処理サービスを市場取引によって得ていた事業者が,特定の産業廃棄物処理業者との継続的な取引に切り替える,すなわち得意顧客になる。このことを図 42に示した。図では,産業廃棄物処理業者を核に,地元コミュニティ及び得意顧客が中心にあり,ここでブランド価値が作り出されている。そして,それを取り巻くマーケットには,潜在顧客及び,ブランドを特に意識せずに処理業者と取引をする市場顧客がある。ここで,処理業者のブランドが市場に浸透すれば,市場にある顧客の一部は得意顧客となり,それがまた処理業者のブランド価値を高めることに寄与する。この配置において,市場にブランドを浸透させるのは,通常は売り手のマーケティング活動である。ここまでの構造は,地元コミュニティが関与すること以外に,一般の物財やサービス財のブランド構造と変わるところは多くない。
国が進めている優良産廃処理業者認定制度は,産業廃棄物処理に関する情報開示を中心とする制度ではあるが,特にマーケティングに対する言及はない。しかし,産業廃棄物処理業者のブランド戦略の中で,市場にブランドを浸透させるためのツールとして活用できる可能性はある。優良産廃処理業者の認定を受ける要件は,情報開示以外それほど難しいものはなく,認定を受けたという事実は,産業廃棄物処理業者のブランド戦略とって有利であるし,国が開示している認定業者リストに掲載されることもマーケティングを展開する上で優位に働くだろう。ただし,こうしたマーケティング上の効果は,制度にビルトインされているものではない。優良業者の認定を受れば自動的にブランド力が強化されるというものではなく,制度に参加する産業廃棄物処理業者が自らの工夫で,マーケティング戦略あるいはブランド戦略に組み込んで行かなければならない。それが出来れば,ブランドの市場への浸透が加速され,市場にあって密接な関係を構築できていない顧客の組織取引への取り込みも促進されることになる。
5 産業廃棄物処理業界の評価尺度としてのブランド
(1) 産業廃棄物処理市場の階層化
ここまでの議論を踏まえて更に推論を進めれば,現在の産業廃棄物処理市場は,既に「ブランド化層」と,「非ブランド化層」が層を形成しているという推測が導かれる。ここのブランド化層では,事業者と産業廃棄物処理業者の双方が,産業廃棄物や環境保全に関する意識と情報処理能力が高く,産業廃棄物処理取引においてはブランドが重要である。一方,非ブランド化層では,産業廃棄物処理取引はコモディティ化しており,事業者と産業廃棄物処理業者は両方とも,情報処理能力が低い(図 43)。
このことが導かれる根拠は次のとおりである。まず,アンケート調査から,事業者の産業廃棄物処理業者選択行動は類型化されることがわかった。このことは,事業者の産業廃棄物に対する意識と情報処理能力の反映であると解釈することが可能である。一方,産業廃棄物処理業者の調査結果からは,各種競争戦略への取組状況に関して類型化したが,これは産業廃棄物処理業者の生き残り(事業継続)能力の反映と理解できる。また,調査協力を呼びかけた約4,000の産業廃棄物処理業者のうち実際に協力した者の数が211であることは,産業廃棄物処理業者においても,産業廃棄物に対する意識と情報処理能力の差があることを表している。以上のことと,産廃ブランドが存在すること,そしてブランドの一般的性質である売り手と買い手の相互作用によってブランドが形成されるということから,ブランド化層と非ブランド化層の存在が推測される。
図 43の上部に位置するブランド化層では,事業者と産業廃棄物処理業者は,ブランドで結ばれた安定的な関係を築いている。一方,下部の非ブランド化層(コモディティ層)では,産業廃棄物処理業者は同業者間で激しい価格競争を繰り広げ,事業者の関心は処理の質などには向かず,専ら価格で廃棄物処理の委託先を決定する。図の左側の縦軸は,事業者と産業廃棄物処理業者が,ブランド化層とコモディティ層のどちらに自身の身を置くかを選択する要因が情報処理能力にあることを示している。
ブランド化層にある事業者・産業廃棄物処理業者も,コモディティ層にある者も,自己の置かれている諸条件と情報において,それぞれが最適解を選択した結果として,ブランド化層あるいはコモディティ層を自身の居場所としていることであろう。だが,条件が許すならば,産業廃棄物処理業者は,過酷な価格競争から脱却できるブランド化層での事業展開を望むだろう。競争が激化する産業廃棄物処理市場において,産業廃棄物処理業者として生き残るという目的に照らした場合,ブランド化層で事業を展開することが有利である。一方,事業者もコストの制約が緩和できるならば,環境リスクが小さく事業者自身の利便性も大きい,ブランド化した産業廃棄物処理業者を選択するだろう。産業廃棄物処理業者がブランド化層に身を置くのに必要な条件は種々あるが,それら条件は産業廃棄物処理業者の情報処理能力に帰することになる。つまり,ブランド化層の優位性を認識し,ブランド確立に向けたマーケティング活動を推進した結果が,産業廃棄物処理業者のブランドであり,産業廃棄物処理業者にそうした行動を取らせるのは情報処理能力なのである。
なお,産業廃棄物処理業者は,事業者に働きかけて事業者の情報処理能力を高めることが可能である。産業廃棄物処理業者を評価する因子として,(1)マーケティング能力,(2)具体的業務処理能力,(3)技術対応能力の3つがあることを第4章で明らかにした。このうちのマーケティング能力とは,顧客との関係を構築・維持するための情報的要素であり,その目的は顧客に働きかけて,顧客の情報処理能力を高めることに他ならないのである。ここでいう顧客とは,事業者であることは当然として,地元コミュニティもまた顧客であることは言うまでもない。
(2) 評価尺度としてのブランド化
実際の産業廃棄物処理市場におけるブランド化層と非ブランド化層の比率を知るには,より大規模な調査が必要になるが,この比率は優良産廃処理業者認定制度の進行の程度を計る尺度になり得る。優良産廃処理業者認定制度は,法律に規定され国が進めている政策であるが,その成果を評価する仕組みが整備されていない。すなわち,優良産廃処理業者認定制度は,産業廃棄物処理業者の外形的な特性が,実際の処理の質に連動するという前提に依拠するものであるが,産業廃棄物処理業者の外形的な特性と,処理の質の関係については検証されていないのである。優良業者に認定を受けた産業廃棄物処理業者数は,一応数値として公表されているが,それが産業廃棄物処理全体の状況を良くしているという因果も相関も示されていない。
仮に外形的な優良業者が産業廃棄物処理の質の向上に貢献するとしても,図 13に見たように産業廃棄物処理を行って価値を作り出すのは,産業廃棄物処理業者だけではなく産業廃棄物処理業者と事業者の協働である。すなわち,優良業者が増えると同時に,優良業者とパートナーシップを組む優良な事業者が増えて,はじめて産業廃棄物処理の質が向上するのである。ここで言う「優良な事業者」とは,産業廃棄物処理業者を選択するにあたり,その産業廃棄物処理のコスト・パフォーマンスを正しく把握評価するだけの情報処理能力を備えた者ということになる。つまり,処理業者の提示する処理価格だけを業者選択のための基準とするのではなく,処理価格に処理の効用(環境負荷や事業者自身の利便性など)を考慮した値(コスト・パフォーマンス)を基準とする事業者である。
国が政策として進める優良産廃処理業者認定制度は,産業廃棄物処理業者の外形的特性を基準とするものの,実際の産業廃棄物処理の質についての基準がないことは述べたとおりである。産業廃棄物処理サービスに対して,国家が求めるべき普遍的かつ最小限の基準を考えれば,おおよそ次のように整理できるだろう。
- 不法投棄・不適正処理を行うリスクが最小であること。
- 環境負荷が小さいこと。
- 事業者(産業)にとっての利便性が大きいこと。
- 合理的コストで供給されること。
- 安定的・持続的に供給されること。
これらから求められる値が,産業廃棄物処理のコスト・パフォーマンスであるが,すべての産業廃棄物処理業者が一律の値をとることはあり得ない。情報処理能力を備えた優良な事業者であれば,産業廃棄物処理業者のコスト・パフォーマンスの差を認識し,産業廃棄物処理業者をコモディティとしてではなく,ブランドとして認識することになるだろう。そのような事業者と産業廃棄物処理業者の組み合わせこそが,図 43上部のブランド化層である。つまり,ブランド化層の大きさが,国の産業廃棄物処理全体の状況を測る指標になると結論づけられるのである。
(3) ブランドの限界
事業(生産)に関する環境負荷と環境保全策の関係を図 40と図 41,そして式1~式6に示し,産業廃棄物処理業者が業務を受託できる条件を導いた。以下には,ここに産廃ブランドを活用することで,産業廃棄物処理業の市場を拡大する可能性について検討する。まず,環境保全策が実施される条件である式6を見ると,すでに高い生産性 P が達成されている状況で,それ以上に高効率な,換言すれば生産性の高い,環境保全策(産業廃棄物処理)を提供しなければならず,そうしたことは売り手である産業廃棄物処理業者にとって容易なことではない。また,式6に対してブランド力という変数を導入することは難しい。次に図 40を検討する。損失Lは,環境保全サービスの買い手である事業者の認識に依るものであることを述べたが,産出Yも部分的には買い手の認識に依る。すなわち,事業者の満足度や,事業者の社会貢献などを産出Yに含めるとすれば,それらは事業者の認識に依るものであり,ここはブランド力を用いた操作が可能である。ブランド力を活用して,「産業廃棄物の委託処理を適正に行うことが産出増につながる」との事業者の認識を獲得するのである。また,事業者が自社の環境対策を公開することで,商品の環境価値をアピールするような場合,ブランドのない産業廃棄物処理サービスでは意味を持たないだろう。そのことを思うと,先に言及した「顧客の顧客戦略」が想起され,また,直接の取引関係のない相手に働きかけるという,産業財マーケティングのソーシャル・マーケティングに近似した側面を強調することになる。
以上のことに気付いた産業廃棄物処理業者が,産業廃棄物の量的な成長が見込めない今後の産業廃棄物処理分野において,最終的に生き残ると考えるものである。
6 産業廃棄物処理業におけるブランド確立の方法
商品ブランドおよび,企業ブランドの価値評価等についての早期の体系的研究として,Aakerの著書(注[104])がある。Aakerは,ブランドの資産価値(brand equity)をブランド・ロイヤルティ,ブランド・アウェアネス,知覚品質,ブランド連想などの要素から構成されるものとし,それら構成要素について評価方法と強化・維持とを論じている。ブランドそのものの価値(brand equity)の本質を論理的に明らかにし,それを実際のケースを多く挙げて検証しており,体系的かつ有益な知識である。しかしながら,研究の対象は,主に消費者製品に係るブランドであり,産業廃棄物処理サービスという産業財については,そのまま当てはめ難い面もある。一方,産業財のブランドについては,Kotlerら(注[105])が,豊富な事例をもとに知見をまとめている。この著作においては,産業財ブランド(B2Bブランド)の構築ないしは再構築の取り組み事例を検証しながら,産業財ブランディングのノウハウを抽出している。しかし,ここには廃棄物処理業やリサイクル業などへの言及はなく,直接の取引相手の他に地域社会への配慮を必要とする環境ビジネスにそのまま適用できない部分が多い。その他にも,ブランド構築について有用な知識を提供する先行研究はいくつかあるが,いずれも本書で明らかにした環境ビジネス特有の構造が考慮されておらず,産業廃棄物処理業のブランド構築にそのまま適用できる知識ばかりではない。
現在までのわが国の産業廃棄物処理業界では,明確な経営意思の下で組織的にブランド構築に取り組んだ例は皆無に等しい。第4章および第5章で取り上げた,高価値ブランドを確立している産業廃棄物処理業者であっても,それは日々の業務をまじめに遂行したことによって築き上げたものであり,明確な経営意思に基づく組織的な取り組みを行った形跡は見られない。筆者は,2007年から2009年にかけて東北の産業廃棄物処理業者70数社を訪問し経営者と接触する機会を得て,産業廃棄物処理業者におけるブランド形成の状況や,マーケティング戦略について尋ねたが,自らのブランドを明確に定義して組織的にブランドの資産価値の確立に取り組んでいる者はなかった。
以上のような状況を前提に,産業廃棄物処理業におけるブランドの確立の方法を検討することとする。
(1) 商品コンセプトを固めること
ブランドとは,自社またはその商品を他社のそれから区別して識別するためのものである。産業廃棄物処理業者が他社から区別されるには,他社とは違う産業廃棄物処理サービスを提供しなければならない。その違いこそ,産業廃棄物処理サービスのコンセプトである。筆者が産業廃棄物処理業の経営者と面談した際に,業者もしくはそのサービスの特長を尋ねたが,経営者は,他社との明確な差別化ができないことの悩みを語ることが多かった。しかし,コンセプトが明確でなければ,他社とは価格競争の中で生きるしかない。
産業廃棄物処理サービスのコンセプトは,シンプルでも構わない。むしろ単純明快なものが良いだろう。産業廃棄物処理業経営者の多くが,他社との差別化に悩むものの,「適正処理をしています」,「他社とは違う丁寧な仕事です」,「機動力があります」などのシンプルではあるが,コンセプトを述べるものがあった。しかし,このような単純すぎるコンセプトは,顧客にとっては当たり前すぎて実感できず,知覚品質あるいは意味的効用につながり難い。こうしたコンセプトをうまく言葉で表現することで,ブランド連想を制御するべきである。たとえば,「適正処理をしています」だけでは単純すぎるが,「頑固なまで適正処理にこだわる」とすれば,このコンセプトを見た事業者は,この産業廃棄物処理業者は少し違うと思うだろう。それだけで,他ブランドとの違いを明確にするというコンセプトの目的は達成されたことになる。そして,コンセプトは,産業廃棄物処理業○○会社というブランドとセットで顧客の記憶に残るのである。
また,産業廃棄物処理業者自身にとっても,「頑固なまでの適正処理」は,あらゆる場面で行動規範になるだろう。たとえば,収集の現場で契約外の異物の積み込みを頼まれた場合,コンセプトを叩き込まれた収集作業員は,それを断ることができる。あるいは,営業マンが顧客と契約条件の詰めの交渉にある時,譲れる条件・譲れない条件の判断の基準となるのがコンセプトである。
なお,このコンセプトは,産業廃棄物処理業者が事業者に訴求して事業者との関係を構築・維持するためばかりでなく,処理施設の地元コミュニティに対する信頼獲得にも活用できるものでなくてはならないことは言うまでもない。直接の取引関係にない人々にとっても,業者ブランドとコンセプトがセットで連想されるようにする必要があるのである(図 14参照)。
(2) 産業廃棄物処理施設で訴求する場合
最新鋭の産業廃棄物処理施設を作っても,それが商品コンセプトに活用されていない例を多く見る。新しく処理施設を設置する目的は,産業廃棄物処理業者の本音では取り扱い規模の拡大によるコストダウンであることもある。しかし,環境基準の厳格化などによって,投資額が巨大になり,規模拡大によるコストダウンも難しいケースが多くなっている。処理施設を作ることで,新しい顧客を獲得できると安易に考えている産業廃棄物処理業者が多いが,それでは現実を認識できているとは言えない。顧客は,施設を買っているのではない。顧客はコンセプトを買ってくれているのである。施設が新しくなっただけで,コンセプトが新しくならなければ,顧客も新しく増えることはない。処理施設は,差別化(コンセプト)とブランド作りに徹底的に活用しなければならない。
最新鋭の大型施設の訴求点が価格競争力だけでは寂しい。まずは,環境パフォーマンスをコンセプトに取り入れることである。「地球環境」や「低排出」などをコンセプトに取り入れるのである。それでも顧客の本音は,環境がどうしてウチに関係あるのか,というところだろう。だから,広告や営業マンの活動など,情報的な操作が必要になる。そういった情報的な操作を駆使して,「信頼」,「安心」,「地球環境への貢献」など意味的性能を事業者が実感するように誘導して行くのである。
完成直後の未使用状態の処理施設は,その施設のライフサイクルの中で最も輝いていて最も魅力的な時期である。処理施設を顧客に見せるということは,物理的性能を見せているに過ぎないが,新品の状態を見せることで,まだ顧客になっていない潜在顧客にも,意味的性能を強く印象づけることができる。ゆえに,新施設はオープン後の1年以内に顧客を獲得しなければならない。埋立処分場なら,完成直後の空虚の状態が一番魅力的である。空の処分場の前で,万全の管理体制でこれから10年計画で埋め立てて行くと説明をすれば,顧客には,「今後の持続性」と「安定性」などを印象づけることができるだろう。この例では,この持続性や安定性こそ,この埋立処分場のコンセプトなのである。
中間処理業者・埋立処分業者の中には,自前の営業マンを持たず,すべてを収集運搬業者の持ち込みにゆだねている者がある。産業廃棄物の排出量は右肩上がりの一本調子で増え続け,処分施設の整備はそれに追い付かないという,バブル期以前の経営スタイルをそのまま続けているケースである。自前の営業をしないのは,産業廃棄物処分の技術的実務に経営資源を集中するということで,妥当な経営判断ではあろう。しかし,それでは自社のブランドが育たず,コモディティとして価格競争にさらされるだけである。中間処理・最終処分のコンセプトを設定してブランドを確立し,それを収集運搬業者に売って貰うのである。少し手間と費用を掛けてブランド戦略にもとづくマーケティングを進めるべきである。ただし,収集運搬業者を押しのけて直接セールスをやることが絶対必要なのではない。収集運搬業者と一緒にそれぞれのブランドを高める努力をするのが最善の方策である。
(3) 収集運搬業者のブランド
収集運搬業者にもブランドが必要である。産業廃棄物をA地点からB地点まで運ぶという単純な機能にしても,商品コンセプトを設定することは可能であるし,必要である。安全に運ぶ,確実に運ぶという当たり前のことでも,他の収集運搬業者との違いを主張しなければならない。特に,収集運搬業者は処分業者と違って,顧客である事業者と直接接触する機会を持っているのである。これはビジネス上の強みと言えるだろう。第2章の図 9に示した5段階モデルにあてはめて見ると,廃棄物を顧客の目の前から除去するというコア効用では差が付かない。ならば,同心円の外方向の機能で差別化することである。客先の廃棄物保管場の掃除の質,収集運搬車両のメンテナンス状況,マニフェスト(産業廃棄物管理票)事務のスムーズさ,どれもが差別化に活用できる要素である。そうした差別化要素を発見したならば,それを商品コンセプトに組み込むことが必要である。
当然ながら,収集運搬業者においても,ブランドとコンセプトは,互いに互いを連想させるものでなければならない。また,産業廃棄物の収集運搬業も環境ビジネスであることを考えれば,直接の取引相手だけでなく,広く社会にそのブランドとコンセプトを受け容れ,理解して貰う努力が必要である。
(4) 環境マネジメントシステムの活用
ISO14001やエコアクション21といった環境マネジメントシステムを導入する産業廃棄物処理業者が増えているが,それをブランド価値を高めるために活用している例は未だ少ない。環境マネジメントシステムを実施する企業などの組織体は,環境方針を設定することになっているが,この環境方針とは別に,企業は普通,経営方針というものを定めている。経営方針と環境方針の2つの規範を設定することは,製造業や卸小売業ならば当然である。なぜならば,それら業種にとっては,環境マネジメントは社内管理の話であって,本業とは別次元の話なのである。しかし,産業廃棄物処理業という環境をビジネスの対象にしている業種であれば,経営方針と環境方針は一致しても良いはずである。つまり,産業廃棄物処理業者の環境方針は,そのまま企業コンセプトとなり,商品コンセプトになるのである。
産業廃棄物処理業でも,CSR(Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任)が流行している。しかし,産業廃棄物処理業にとっての最大の社会貢献は,自社の産業廃棄物取扱量を増やすことである。X社という産業廃棄物処理業者があったとして,それが他のどの産業廃棄物処理業者よりも環境負荷の小さい処理をしているのならば,X社が処理をするのが最も地球環境に良いはずである。X社自身が,そう信じることができれば,自ずと環境方針をベースとしたコンセプトと経営方針が出来るはずである。X社は,CSRらしいことをせずとも環境負荷の小さい処理に専念していれば,事業者は,X社に産業廃棄物処理を委託することによってCSRを果たすことができるのである。
(5) ブランド浸透
産業需要家が買い物をするプロセスは,案件化とブランド選択の2段構えになっていることが知られている。そのことを理解すると,ブランドを浸透させる方法が見えてくる。買い物プロセスの始まりは,事業者において産業廃棄物処理を新しく委託する,あるいは現在の産業廃棄物処理業者を変更することが社内で話題になること,つまり案件化することからである。新しい産業廃棄物が発生するようになったのかも知れない,もしくは,現在の産業廃棄物処理業者に不満をおぼえたのかも知れない。とにかく第1段階は案件化である。その後に続くのが,ブランド選択である。いくつかのブランドを並べて比較し,その中から最良と思うブランドを選ぶが,この段階で選ばれるのは,当然のことながらブランドが付いた産業廃棄物処理業者である。
さて,2段階プロセスということは,産業廃棄物処理業者にとって機会が2度あるということである。その2度の機会は,一方がチャンスで他方はピンチである。産業廃棄物処理業者にとってのピンチとは,現在の顧客が産業廃棄物処理業者の変更を案件化することである。そういうピンチを招かないように,注意を怠らないことである。顧客が市場取引に魅力を感じないようにすることが必要である。そのためには,日々の仕事をきちんとして常に満足を与えるようにしなければならない。特に,ブランドの価値を維持して,他社と比較されないようにすることが大切である。
まだ取引が始まっていない潜在顧客に対しては,案件化のあとのブランド選択の段で選択肢に入れて貰うための広告やセールスなどの行動をとるべきである。しかし,広告やセールスをしても,すぐには売上が増えないことは予め理解しておくべきである。人間の判断の仕組みを調べると,脳内の長期メモリーという機能が重要な役割を果たしていることは,第5章に図 36として引用した。自社のブランドやコンセプトを未来の顧客の長期メモリーに留めてもらうことが,広告やセールスの目的である。ただし,長期メモリーに知識を保存するには,1つ条件があって,整理されたかたちで保存しないと,あとから上手く引き出せないという。しかし,ブランドは記憶の検索のためのインデックスになるのである。第5章で述べたことであるが,敢えて繰り返しておく。一方で,産業廃棄物処理サービスの顧客は企業組織であり,人間でない組織に長期記憶などあるものか,という反論があるかも知れない。それに対しては,アンケート調査によって明らかにしたように,産業廃棄物処理業者の選択には事業者の会社内の多くの個人が関わっていて,組織の意思にはそれら複数人の価値判断が反映されているという事実で応じよう。
(6) 広告とパブリシティ
産業廃棄物処理業者が新聞や雑誌の記事となることがある(不祥事以外)。それらは,タイアップ記事とか,パブリシティと呼ばれる一種の広告手法である。それと,本来の広告も見られる。こういった紙媒体への露出は重要である。第5章で見たように,産業廃棄物処理ブランドの評価は,顧客である事業者による総合評価であるが,それは大きく3つの要素から成る(図 31参照)。1つは,実際に産業廃棄物処理サービスを受けた実感,つまり物理的性能評価である。2つめは,社会から得られる評価である。3つめは,売り手である産業廃棄物処理業者が発信する情報である。広告は,3つめの要素に含まれるものと理解できる。パブリシティは,2つめの評価に見せかけた3つめの要素である。さて,3つの評価要素のうち,物理的性能評価は,実際の顧客でないとできない評価である。しかし,広告は実際の顧客だけでなく,潜在顧客や,顧客の顧客など物理的性能評価できない人々に働きかけることができる。このことを理解すれば,広告の目的や,対象とすべきターゲットも自ずと理解できるはずである。もちろん,広告には実際の顧客に直接働きかけて,そのブランド評価の補助をする意味もある。
広告では,何を伝えるのかも重要であるが,誰に伝えるかが重要である。普通,商業広告で伝えるものは,商品コンセプトとブランドである。むしろ,コンセプトやブランドがなければ,広告で伝えるものなど何も残らないと言うべきだろう。広告の目的は,ターゲットの記憶に入り込むことである。すなわち,ターゲットの長期メモリーに整理された情報を送り込むことである。誰の記憶に入り込むかが問題ではあるが,誰をターゲットにしても,伝える内容は商品コンセプトとブランドであることには代わりはない。ターゲットに合わせて,表現方法や内容の詳しさ等には変化をつけることにはなる。この頃は,産業廃棄物処理業者が新聞のかなり大きな紙面をつかって,イメージ広告を出す例を見るようになった。直接の顧客ではない,市井の人々をターゲットとするものである。しかし,それらの多くは無意味である。市井の人々に訴求すること自体は有意義であるが,それらイメージ広告は,筆者の記憶には画像以外は,ブランドすらも残っていないのである。やはりブランドはコンセプトと対になっていないと,記憶に残りづらいようである。イメージ広告にしても,最低限伝えるものは盛り込まないと,それは単なる風景写真になってしまうのである。
7 残された課題
(1) ブランド調査の難しさ
これまで,家計消費財に関して様々なブランド調査が実施されているが,産業財に関する調査は多くはない。既往のブランド調査については,その評価尺度やスコア算出方法は様々であり,また,それらが公開されていない例もある。すなわち,ブランド調査の方法にはスタンダードが存在しないというのが実状である。一方,ブランドとは,そのカテゴリーの財貨に関わりの強い者にとってだけ意味のあるものであり,そうしたブランドの概念と大標本・無作為調査とは相容れず,ブランド調査の対象とすべき範囲は,その分野に関わりのあるものとするのが良いとの指摘がなされている(注[106])。この理論に基づく調査として,ブランド・ジャパン委員会と日経ビジネス誌が2001年より毎年継続しているブランド・ジャパン調査がある(注[107])。ブランド・ジャパン調査では,企業人と一般消費者を調査対象とし,企業名と製品名を分けずにアンケート調査することで,企業ブランドと消費者ブランドについてブランド総合力を出している。本研究が,産業廃棄物処理業者と事業者の両方に対する調査としたことも,この考えを参考にしている。
本調査における産業廃棄物処理業者の回答者数は,全国10数万の許可業者のうちの211であり,サンプルの偏向を考慮する必要があろう。しかし,偏向の要素として考えられるのは,産業廃棄物に対する関心の程度と,情報処理能力の程度である。今回の調査で得られた以上のサンプルを収集できたとしても,すなわち産業廃棄物処理に対する関心と情報処理能力が低い者の回答を得たとしても,それらは回答者の乏しい情報から導かれたものであって,列挙される優秀処理業者名がさらに拡散したことであろう。事業者についても,産業廃棄物処理業者に対すると同様にサンプルの偏りはあるが,その回答については,産業廃棄物処理業者のそれと同様の理由で,分析に堪えるだけの精度を確保できていると考える。サンプル抽出の妥当性は,事業者が挙げる優秀業者名と,産業廃棄物処理業者が挙げるそれについて,価値基準の一致が見られたことによって裏付けられる。
アンケートの結果をもとに分析し,産業廃棄物処理サービスの取引において産業廃棄物処理業者のブランドが重要な働きをしていることを明らかにした。しかし,サンプルの規模を考えれば,結果の解釈にあたり「産業廃棄物処理業者と事業者のうち,特に産業廃棄物に対する関心と,情報処理能力が高い者については」という限定をするべきである。この限定によって,「ブランド化層」と「非ブランド化層(コモディティ層)」に階層化しているという仮説が導かれた。
(2) ブランド弱者の存在意義
本書では,ブランド力の強い産業廃棄物処理業者の,今後の展開のシナリオとして予測される事業者との協働化を示した。そして,現在既にブランド化層と,非ブランド化層の階層化が進んでいることを推論した。こうした流れが進展して行くことは,一方で協働化事業やブランド化層に入れない産業廃棄物処理業者と事業者が残ることを意味する。すなわち,産業廃棄物処理のブランド化と並行して,コモディティ化した産業廃棄物処理取引,コモディティとしての産業廃棄物処理サービスを購入する事業者,そしてコモディティ化した産業廃棄物処理業者が存在することになる。本書で主張してきたのは,ブランド化しない(コモディティ化した)産業廃棄物処理業者は,優良な産業廃棄物処理業者ではないという理論である。しかし,ブランド力が弱い業者に存在意義はないのか;棲み分け,役割分担があるのではないかという疑問が残る。
また,ある時点で差別化を謳い高価値ブランドを確立した商品であっても,市場が成熟するにつれ,他ブランドとの差が縮まり,コモディティ化することがある。この場合,当該製品の品質が劣化したのではなく,他製品の品質が良くなり,その商品カテゴリー全体が高いレベルを達成しながら同水準化してしまうのである。産業廃棄物処理の世界がそのような状況になれば,買い手である事業者は,どのような産業廃棄物処理業者を選んでも必要な品質の産業廃棄物処理サービスを手に入れることができるようになるだろう。その時,上述のような産廃ブランドは意味を持たなくなるだろうか。
あるいは,現在衰退期にある産業廃棄物処理業は,やがて停滞期に向かうだろう(表 4参照)。衰退する業種の企業が執り得る競争戦略は,多くはない。ブランド力の弱い産業廃棄物処理業者が,これから投資をして高価値ブランドの確立を目指したとして,すでに高価値ブランドを確立して累積経験量を積む者に追いつくことができるのだろうか。これらのことについては,さらなる検討が必要である。
(3) ブランド化と不法投棄の関係
本研究では,ブランドを確立することが,産業廃棄物処理業者のあるべき姿であることを実証的調査の結果と,種々の知識から理論的に導いた。すなわち,産業廃棄物処理業者のブランド化が進めば,不法投棄・不適正処理が減るであろうことが予測されるのであるが,このことは現段階ではあくまでも理論仮説に過ぎない。これまで,産業廃棄物処理業者のブランド化の程度を測る組織的な調査がなく,それを証明する術がないのであるが,今後の調査による証明が必要である。
脚注
(注[99])本節の主要部分は,上田晃輔「産業廃棄物の流通構造-交変系概念への適用」『流通情報』,44巻2号,2012年7月,47-61ページに詳細を記述した。
(注[100])陸上で発生した廃棄物を船舶等を用いて海洋投棄する,あるいは洋上焼却することは,1996年に採択されたロンドン条約議定書によって,事実上全面禁止されている。それ以前は,わが国でも,アルミ精錬工程から発生する安定な汚泥や,各種の化学廃液(主に酸,アルカリ)のうち無害なものなど,年間に1,000千万トン程度の産業廃棄物を海洋投入処分していた。
(注[101])Kotler, P., Marketing Management: 11th edition, international edition, Prentice Hall Edition, 2003, pp. 418-424.
(注[102])余田拓郎,首藤明敏『B2Bブランディング – 企業間の取引接点を強化する』,日本経済新聞社,2006年,34-37ページ。脚注93参照。
(注[103])上原征彦『マーケティング戦略論』,有斐閣,1999年,68ページ,140ページ。
(注[104])Aaker, David A., Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name, THE FREE PRESS, 1991.
(注[105])Kotler, P. and Pfoertsch, B2B Brand Management, Springer Berlin, 2006.
(注[106])片平秀貴『新版パワー・ブランドの本質』,ダイヤモンド社,1999年,40-53ページ。
(注[107])小林直樹「ブランド・ジャパン2001 -1万人のブランド調査」『日経ビジネス』,2001年5月21日号,98-100ページ;ほか各年調査の記事が日経ビジネス誌に掲載されている。

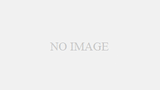
コメント