第3章 産業廃棄物処理業の問題点
産業廃棄物処理業の機能は,読んで字のごとく,産業廃棄物を処理することである。そして,産業廃棄物処理業が取り扱いの対象とする廃棄物とは,マイナスの価値を有する物体バッズ(bads)であり,産業廃棄物の処理に係る問題の多くは,廃棄物がマイナスの価値を伴うことに起因すると考えられている。
1 施設立地の困難さ
廃棄物処理施設は,迷惑施設あるいは嫌悪施設とされ,その立地に関して紛争を抱えるケースが多い。廃棄物処理施設は,公衆衛生の向上と生活環境の保全を目的とするものであり,本来は環境施設あるいは衛生施設と呼ばれるべきものである。しかし,都市ごみ処理施設・産業廃棄物処理施設ともに,計画段階および稼働後に紛争を発生するケースが多く知られている。1997年8~9月の調査では,全国の約20%の自治体がごみ関連施設の立地紛争を抱え,その施設種類別内訳では,焼却施設62.4%,最終処分場57.1%,リサイクル施設15.8%である(注[40])。また,国が承認し財政支援する資源化施設整備事業であるエコタウン事業に関するアンケート調査では,住民問題の有無の質問に対して,71施設のうち問題あり7,なし38,無回答26という結果が得られている(注[41])。
紛争を解消し,合意形成に至った事例については,そのプロセスは興味深い。これまでの研究では,嫌悪施設の立地を円滑に進めるためには,ステイクホルダー間の信頼関係を構築することが重要であるとし,科学的妥当性,計画への参加,手続きの妥当性,適切な補償が必要であるとされている。
迷惑施設の立地問題は,受益と受苦の非対称性にあるとされている(注[42])。迷惑施設の代表例として,都市ごみ焼却施設や産業廃棄物埋立処分場のような廃棄物処理施設が挙げられる。都市ごみ焼却施設を例にとれば,施設の便益を享受するのはその市の市民全員である一方,施設の環境影響を被るのは,施設周辺の地元住民である。施設の環境影響が完全に制御されたとしても,地元住民はつねに施設の存在そのものについて日常的にリスクを感じるが,これも受苦である。受益と受苦の配分や補償についての公正概念は,受苦と受益の配分に関する分配的公正性と,分配を決める手続き的公正性に分けて捉えられるという。両者は密接不可分であるが,前者の領域では,どこに立地するか,どのように補償するかなどが評価され,それらを決める過程で誰が参加してどのような議論を経て決定に至ったかなどは,手続き的公正性の領域で判断すべきだという。
迷惑施設の立地問題に関する研究や,NIMBYに関する研究は,政治経済学・都市経済学・地域経済学などの観点から,補償スキームや立地の最適解を求めるもの(注[43]),あるいは,実際の紛争事例の経過を記述した研究が多い(注[44])。しかし,立地に関する紛争とその解決までの過程は,ステイクホルダー間での交渉と,それによる関係の変化であり,こうした動態の分析には,マーケティング分野での知見の応用が有効だと考えられるものの,これまでそうした視点に立った研究はほとんど実施されていない。事例を分析し,体系化するためのツールとして,マーケティング分野での知見の応用が期待される。本研究では,マーケティング分野の分析手法のひとつであるS-Dロジックを応用して,環境問題の本質を知る糸口を掴んだところである。そのことは,第2章に記述したとおりである。
2 不法投棄・不適正処理
(1) 不法投棄の状況
廃棄物処理に関する最大の問題は,不法投棄・不適正処理である。特に,廃棄物の不法投棄・不適正処理は,環境事犯の大部分を占めており(表 7,表 8),事態は深刻であるとされている。不法投棄は,マイナス価値のものを民間処理することに起因するとされる。廃棄物は,媒体シフトした汚染物質の最終的な行く先であると同時に,環境問題の最終的な行く先でもあることは皮肉である。
表 7 環境犯罪の法令別検挙件数の推移(注[45])
表 8 廃棄物処理法違反の様態別検挙件数(平成22年度)(注[45])
環境省の発表によると,2010年度に新規に判明した産業廃棄物不法投棄事案は,216件,投棄量にして6.2万トンである。不法投棄事案とは別に,不適正処理事案が191件,不適正処理量6.4万トンが挙げられている。不法投棄事案のうち2件は投棄量5,000トン以上の大規模事案であり,その投棄量の合計は2.6万トンで全体投棄量の41.9%になる。また,不法投棄された産業廃棄物の種類を見ると,建設系のものが件数にして72.7%,投棄量で68.8%を占めているという。図 17に各年度の新規判明不法投棄事案の件数等に関するデータを,図 18に平成22の不法投棄の原因者に関するデータを示した。
図 17 産業廃棄物の不法投棄の新規判明件数と量の推移(環境省)(注[46])
図 18 不法投棄原因者(平成22年度 環境省)(注[46])
図 19 原因者別不法投棄量 (平成22年度 環境省)(注[46])
なお,犯罪統計とは,その時に明らかになった事案についての統計であり,真の犯罪数を正確に反映しているかは,慎重な検証を経なければ確認できないことに注意が必要である。また,産業廃棄物の不法投棄に関するデータは,その年度に新たに判明した不法投棄事案に関するものであり,実際の不法投棄を反映した数値であるかは断定できないことにも注意が必要である。
(2) 不法投棄のメカニズム
不法投棄事案・不適正処理事案のうち,近年注目されるのは,投棄量5,000トン以上の大規模な事案である(注[47])。香川県豊島事案(約56万立米),青森岩手県境事案(約109万立米)(注[48]),秋田県能代事案(約101万トン)(注[49]),福井県敦賀事案(約119万立米)などが代表的なところである。これらの超大型事案は,正規の許可を受けた産業廃棄物処理業者によって引き起こされたものであり,無許可の処理請負人や,事業者によるものでないことが特徴である。正規の許可のもとで数年以上にわたり不適正な処理を続け,それがある時期に倒産するか,摘発されるかで事案になる。
石渡(2002, 2003)は,不法投棄・不適正処理のメカニズムを分析している(注[50])。石渡は,不法投棄は,産業廃棄物処理市場のひずみが生み出した経済犯罪だとし,事業者や産業廃棄物処理業者の会計帳簿を分析することで不法投棄の事実やその経路を割り出すことができるとしている。石渡が環境省統計における総排出量と埋立処分量等から推計した不法処分量は,年間4,000万トンという数値になる。年間の不法投棄新規判明量が40万トン前後で推移していることと比較すれば,判明した不法投棄量の100倍に達する産業廃棄物が発覚しないまま不法に処分されていることになる。
石渡はまた,大規模な不法投棄事案では,産業廃棄物は先ず正規の処理業者に引き渡され,そこから不法投棄ルートに潜り込むとしている。不法投棄メカニズムの詳細は,(1)産業廃棄物を中間処理施設に持ち込む,(2)中間処理施設では持込量に応じて処理効率を調節し,処理容量をオーバーする分は処理残渣として処理施設から搬出する,(3)搬出された処理残渣を不法に埋め立てるというものである。以上は中間処理施設が不法処理ルートの入口になっているパターンである。
もう1つのパターンは,埋立処分施設が不法処理ルートの入口となっているものである。(1)残余容量が小さい埋立施設は,なんとか埋立を満杯にしないで営業を続けたいと考える,(2)既に埋め立ててある産業廃棄物を掘り起こして新規受入容量を確保する,(3)掘り起こした産業廃棄物を不法投棄ルートで再処分する。又は,(2’)書類を偽装して産業廃棄物の受入を続ける,(3’)偽装して受入れた産業廃棄物を不法投棄ルートで処分する。
多くの研究が,不法投棄は大規模化の傾向にあるばかりでなく,地理的に集中する傾向にあることを明らかにしている(注[51])。不法投棄しやすい条件はどこでも容易に揃うわけではなく,諸条件が揃う場所に集中するのである。なお,集中するのは不法投棄ばかりでなく,産業廃棄物処理施設も集中することがある(注[52])。相続に関係して適当な土地があることなどによって,産廃銀座と呼ばれる地区が形成される例がある。産業廃棄物処理施設が狭い地域に集中した場合,実際は不法投棄・不適正処理とは関係ないにしても,集中することで迷惑がられることになる(注[53])。それが,産業廃棄物処理施設の一般的なイメージ悪化をもたらしている。
ここまで述べた不法投棄の構造を,産業廃棄物処理に係る諸々の問題の中に位置づければ,図 20に示すような循環として整理することができる。この悪循環は,増幅的悪循環であるといえる。
図 20 不法投棄の悪循環(全国産業廃棄物連合会)(注[54])
バッズの処理を受託した者は,不法投棄によって費用を節約することができる(注[55])。また,不法投棄を行った場合でも,摘発・検挙に至らなければ,顧客に不利益を与えることもない(注[56])。それゆえに,一般の財貨の取引であれば粗悪品を商う商人は速やかに市場から排除されるのに対し,産業廃棄物処理では不法な処理をする者が比較的長期にわたり活動を続けられる。その結果,不法投棄・不適正処理案件は大型化するのである。
3 不適正処理と法規制の矛盾
(1) 法規制の矛盾
廃棄物処理法は,一般廃棄物(主にごみ)と産業廃棄物の両方について規定している。一般廃棄物については市町村による処理を基本とする行政法の性格が強い反面,産業廃棄物については事業者と処理業者に対する規制法・取締法の性格が強い。
廃棄物処理法は,これまで数度にわたる改正が実施され,産業廃棄物処理に対する規制が大幅に強化されてきたが,産業廃棄物処理施設の設置促進のための有効な方策はほとんど講じられてこなかった;産業廃棄物処理施設,特に埋立処分施設の設置は,もともと容易ではないが,法律の支援がないことがそれをさらに困難にした;このことが不法投棄を誘導しているとの指摘がある。すなわち,埋立処分場の不足によって行き場を失った産業廃棄物が,不法投棄されるというのである(図 20)。不法投棄の悪循環は,産業廃棄物処理業者の全国組織である公益社団法人全国産業廃棄物連合会も認識し,公式見解としているところであり,図は同連合会のパンフレットから引用したものである。
施設設置の困難化は,施設配置の歪みをもたらした。産業廃棄物処理施設の配置は,産業廃棄物処理の需要ではなく,地方の規制の強弱に応じたものとなった。施設配置と処理需要の不適合は,産業廃棄物の好ましくない移動を引き起こし,地方行政に産業廃棄物の流入規制を導入させるに至っている。それら持込規制は,多くの場合,事前協議という形を取っている。事前協議とは,県外の産業廃棄物を処分しようとする場合に,事業者もしくは産業廃棄物処理業者から行政に届出書を提出させ,それに対して必要な行政指導を行うものである。
また,すでに述べたとおり,廃棄物処理法は産業廃棄物処理行程における商社の仲立ちを嫌っている。そのことにより,産業廃棄物処理についてはオープンな市場が形成されず,結果として産廃流通(物流および商流)は大規模化することなく,産業廃棄物処理業者の経営規模も大きくならないと指摘されている。現在,環境省が中心になって進めている「優良産廃処理業者認定制度」は,オープンな市場の形成を目標としていると考えられるが,それは現在の法律が規定するフレームワークとは矛盾する。
更に,廃棄物処理法は,産業廃棄物の物流についても厳しい規制を設けている。産業廃棄物処理施設での廃棄物の保管に厳しい数量制限を付しているほか,運搬途中での積替えや保管についても厳格な規制が適用される(注[57])。リサイクルは主に工業原料となる資源の市場変動を吸収するためにストックを必要とするが,経済合理性を無視してリサイクル目的の積替保管までが制限されるために,リサイクルが阻害されていると言う。一方で,リサイクルに名を借りた大規模な不法投棄に対して法律は無力である。
図 20の伝統的な不法投棄の理解に,悪徳産業廃棄物処理業者の関与を加味して図示したものが図 21である。不法投棄の悪循環を回すのは,悪質な産業廃棄物処理業者であり,そのような悪質業者の存在を許しているのは,情報不足であるとの通念のもとに,優良産廃処理業者認定制度をはじめとする諸政策が進められている。
(2) 優良業者認定制度
廃棄物処理法が一部改正され,平成23年4月から「優良産廃処理業者認定制度」が実施されている。これは,(1)情報公開,(2)行政処分歴,(3)環境マネジメントシステム,(4)財務状況,(5)電子マニフェスト(注[58])への参加状況を評価項目とし,それぞれについて所定の要件を満たす産業廃棄物処理業者を優良産廃処理業者と認定して,業許可の期限を通常の5年から7年に延長するなどの優遇を与えるものである。優良産廃処理業者認定制度を導入するためのパイロット事業として,環境省は平成16年度から「産業廃棄物処理業優良化推進事業」を実施してきた(注[59])。平成16年からはじまる一連の事業の目指すところは,産業廃棄物処理業者の情報開示を進めることで,優良な業者を伸ばし,悪質な業者を駆逐するというものである(注[60])。しかし,環境省の公式資料には「排出事業者が自らの判断で優良な処理業者を選べるように」とあるだけで,優良な業者の要件が定義されて来なかった。このような曖昧さは,この事業が都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者を優良か否かで差別化しようという政策であるが為に,優良性の明確な定義が難しいことに起因するものと考えられる。だが,これまでの施策の流れや,関係者の意識などからは,「優良でない産業廃棄物処理業者とは,不法投棄(不適正処理)が実行されないまでも,そのリスクあるいはポテンシャルが高い産業廃棄物処理業者」であるという定義が共通の認識になっている。
不法投棄が実行された場合には,取り締まり・責任追及と並んで,原状回復措置(環境修復工事)がなされるが,国の政策は不法投棄の潜在的な可能性を低減することに主眼が置かれるようになっている(注[61])。そして,産業廃棄物処理に係る諸問題は最終的には不法投棄(不適正処理)に帰せられると認識されている。
4 不適正処理の社会的影響
(1) 規制強化
これまで,不法投棄・不適正処理が更なる規制の強化をもたらしてきた。これは,行政および立法セクターが,不法投棄・不適正処理対策として規制強化以外の方法を知らなかったからであるし,行政当局が取り得る対策は規制に基づく取締と指導に限られていたからである。
規制強化の方向は,基本的にプロセス規制(工程規制)である。出口規制(結果規制)であれば,規制を受ける者にとってはオペレーションの自由度が高く,イノベーションの動機も強まるが,工程規制では手続きが煩雑になり,イノベーションを阻害することが多い。たとえば,廃棄物処理法については,ダイオキシン問題を契機に焼却に係る規制が強化されたが,そこでは煙突から放出される廃ガスの成分や煤じんの濃度を規制するばかりでなく,炉内の燃焼温度や廃棄物を炉内に送り込む方法まで細かく規定するようになった。
(2) オープンな市場の欠如
バッズ取引では,段階を重ねると情報が保存され難くなる,すなわちバッズの行方を追跡することが困難になり,責任の所在が不明確になることが指摘されている(注[62])。そのため,廃棄物処理法は不適正処理を防ぐためとして,産業廃棄物処理業者から産業廃棄物処理業者への再委託を原則禁止してきた。また,事業者と産業廃棄物処理業者の間での契約を細かく規定しており,仲立ちが存立する余地が小さい。これら過剰な規制が,産業廃棄物処理においてオープンな市場の形成を阻害してきた要因の一部になっていると考えられる。また,前述の地方行政による県外廃棄物流入規制も,市場の範囲を狭め,そのオープン化の阻害要因になってきたと言えるだろう。
ここでいう「オープンな市場」とは,(1)参入がオープンであることと,(2)需要家がサプライヤーを容易に探索できること,そして(3)サプライヤーが需要家と容易に関係を作れることの3つを同時に満たす場をイメージすることとする。
オープンな市場が存在しないことの影響とは何かを考える。需要家に対する影響は,探索意欲の抑制であろう。産業財の購入プロセスは,まず財貨の購入が案件化され,次いで取引先の選択がなされることが明らかにされている(注[63])。オープンな市場が存在しなければ,需要家は購買を検討するために比較すべき代替案に触れる機会がないために,問題意識を持ち得ず,案件化することもないであろう。サプライヤーである産業廃棄物処理業者への影響は,マーケティング活動の停滞である。需要家が探索意欲を持たないことと,世間体を気にする事業者は容易に産業廃棄物処理業者をスイッチしないこと故に,いったん顧客との関係を構築した産業廃棄物処理業者はマーケティングに注力する必要がない。ただし,世間体を気にしない顧客に対しては,処理価格がほとんど唯一のマーケティング手段となる。
このようなマーケティングの停滞によって,産業廃棄物処理に関しては,流通面と技術面の両方でイノベーションが進まなかったのである。
(3) 住民合意のさらなる困難化
産業廃棄物は施設において処理される。また,リサイクルを行うのも産業廃棄物処理施設である。産業廃棄物処理施設を設置するに際して必要な要素は,通常のヒト・モノ・カネ以外に,産業廃棄物特有の要件として,近隣住民の同意がある。もともと住民同意とは,都道府県行政が産業廃棄物処理施設の設置の許可を行う際に,施設設置者と地元住民との調整を確実なものとし,そのことを確認するために,許可権者である地方行政当局が施設設置者に対して求めたものであった。当初は,地方行政の非公式な事務手続きであったが,不法投棄によって産業廃棄物処理のイメージが悪化するにつれて住民は容易に同意しなくなってきた。また,産業廃棄物処理施設の設置を望まない住民は,同意の制度を盾として反対活動を展開するようになった。
こうして住民同意が産業廃棄物処理施設設置の障害になるに及び,平成9年になされた廃棄物処理法改正において,施設の設置に際しての地元調整手続きが明文化され,それまでの地方行政の非公式な事務手続きから,法律の規定する要件になった。このことにより,産業廃棄物処理施設の設置には,従来以上に時間と労力を必要とするようになり,施設不足がますます深刻になった。
(4) 産業廃棄物処理業の大規模化の阻害
廃棄物処理は,規模の経済が働く。不法投棄がオープンな市場の形成を阻害する要因となったことは述べたが,オープンな市場が形成されなかったことが,産業廃棄物処理業の集約化,大規模化を妨げてきたとの仮定が成り立つ。
また,不法投棄による産業廃棄物処理のイメージ悪化は,大資本の産廃ビジネスへの参入を躊躇させてきた。1990年代以降,セメント製造業や鉄鋼業が産業廃棄物処理分野に進出するようになったが,リサイクルや環境といったコンセプトが社会的に定着して産業廃棄物本来の悪いイメージを打ち消すだけの力を持つようになってからのことである。ただし,産業廃棄物分野に進出した大企業であっても,いまだに埋立処分には手を付けていない。セメント焼成炉や製鉄の高炉といった既存の設備と技術を応用できる範囲にとどまっている。
5 環境ビジネスの成立条件
バッズを取り扱う業を静脈産業,あるいは環境ビジネスと言う。産業廃棄物処理業は環境ビジネスに含まれる。産業廃棄物処理業とその問題点の本質を理解するには,環境ビジネスの成立条件について知る必要がある。
(1) 環境規制の必要性
環境ビジネスが成立して経済成長に貢献するということは,税金による補助がなくても自立的に環境ビジネスが存立するということである。そのためには,環境ビジネスが付加価値を創造しなければならない(利潤を上げられなければならない)。しかし,人為的な制度の整備がなければ,環境ビジネスは付加価値を生まない。すなわち,環境ビジネスが付加価値を創造するようにするには,環境ビジネスに貨幣価値を規定するレジームを政策によって設定しなければならないという(注[64])。
社会・経済システムには,環境規制がない場合,廃棄物発生抑制メカニズムが働かないし,バッズの処理に金を掛ける必然性もない。環境規制がない状態では,廃棄物は海や川に流す,あるいは野天で焼いて未処理の煤煙として大気に放出すれば良い。そのことを理解すれば,環境規制が存在することによってはじめて産業廃棄物が存在することが分かる。また,環境に貨幣的価値を認めない状態であれば,廃棄物の処理に金を掛けないことが企業や個人にとって最も経済合理的な行動である。そのような経済的な性質を有する廃棄物の処理を民間の経済活動として成立させるには,法律その他の規制によって廃棄物処理の責任を明確にしなければならない。
そして,バッズを扱う経済で特に注意が必要なのは,ミクロ経済とマクロ経済の乖離があることである。そのことについては,後に詳しく論じる。
(2) オープンな市場の必要性
オープンな市場とは,参入が自由な市場のことである。交換の場である市場は,通常は参入障壁がない方が,効率的な資源配分がなされる。すなわち,市場の特定の固定的なメンバーに取引が集中するのではなく,最も効率的な取引を提供し得るメンバーが取引するようになれば,より少ない貨幣でより多くの財貨を手に入れることができるようになる。このような状態を効率的な資源配分と言う。このことは,バッズ経済についても例外ではない。環境対策費用も,市場メカニズムに基づいて負担されるのが効率的であるとされている。具体的には,費用低減と技術開発であり,これらを促進するには,競争圧力が必要である。バッズ市場のオープンアクセスについては,グッズ市場のそれのように単純でない側面があり,場合によっては環境に悪い影響をもたらすことがあるので注意が必要である(注[65])。
(3) 環境対策行動におけるミクロ経済とマクロ経済の乖離
ある環境対策行動が,トータルの社会費用を最小にするものであることがわかっていても,その当事者にとっては利益にならないことがある。それが,環境対策行動におけるミクロ経済とマクロ経済の乖離である。たとえば,飲料容器(一般廃棄物)の処理に関しては,市町村のごみ処理システムで処理するよりも,事業者に容器の回収・再資源化の責任を負わせた上で,事業者の負担は飲料価格に転嫁する方がトータルの社会的コストは抑制されると考えられているが,法的な枠組みがなければ,事業者が自ら飲料容器の回収に乗り出すことはあり得ない。このような状況で現在のような回収・再資源化システムを稼働させるには,拡大生産者責任理論にもとづく容器包装リサイクル法が必要だったのである(注[66])。
このことは,産業廃棄物についても例外ではない。現在の産業廃棄物処理体系が立脚する汚染者負担原則は,廃棄物処理費用を外部費用とせず内部化することによって,資源の効率的配分を目指すものであって,そのことによって産業廃棄物処理に係るトータルの社会的費用は最小化されるはずであり,内部化した費用を製品価格に転嫁できれば事業者の費用負担も公平化され,不法投棄の動機もなくなるはずである。しかし,それが困難であるのが現実である。
(4) 自由参入および退去の問題点
バッズ事業では,事業遂行の能力やモラルが低い者の参入があっても,グッズ事業の場合のように排除(淘汰)され難い。通常の財貨であれば,需要家の要求を満たさない質の低いものは買い手が付かず,そのような粗悪品を供給する者は自ずと淘汰され市場から退去させられることになる。しかし,廃棄物処理というサービス財に関しては,需要家の関心は基本的に処理価格だけであって処理の質は考慮されず,それゆえに質の低い処理サービスでもそれを買う者が存在し,質の低い業者であっても淘汰され難いと言われる。このように,放任状態では産業廃棄物処理業の質は向上しないので,何らかの人為的な操作が必要であると言われてきた。
また,バッズ事業から業者が退去する場合,未処理のバッズ在庫を大量に放置したままになることがある(図 11 ,図 10参照)。通常の財貨では,商品が売れないために不良在庫が増え,その結果その企業は倒産ということになる。その場合,不良在庫であっても債権者は残った在庫を押さえて,債権の回収にあてることができる。しかし,バッズの場合は残された在庫は債務そのものであり,その処理は債権者負担もしくは公費負担に依らなければならない。現在問題になっている不適正処理の大型事案は,ほとんどがこの構図である。たとえば,不法投棄大型事案の代表例としてあげられる,青森県と岩手県の県境で発覚した事案である。埼玉県で焼却などを行っていた業者から青森県の処分業者に首都圏の産業廃棄物157万トンが持ち込まれ,岩手県との県境にまたがる原野に埋められた。不法に埋められた産業廃棄物が生活環境の支障になるとして,県知事は原因者に対して原状回復の措置命令を下したが,埼玉県の業者は2000年に破産,社長が自殺した青森県の業者も2001年に解散し,措置命令を実行するものがいなくなった。2002年から両県による行政代執行の形で原状回復作業が始まった。産業廃棄物の不法投棄に係る行政代執行に関しては,その費用を国庫補助および地方債の起債特例などによる支援を規定する「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」が施行されている。青森・岩手県境案件も特別措置法による国からの財政支援を受けている。
産業廃棄物処理事業においても,基本的に市場のオープンアクセスは確保されるべきであるが,上に述べたような産業廃棄物の特異性に対処するための制度の補強は必要である。
6 通念
(1) 産業廃棄物処理に関する通念
ここまで産業廃棄物処理業の諸問題を見てきたが,それらを根拠として幾つかの通念が形成され,産業廃棄物処理業界とその周辺に様々な影響を及ぼしている。
その1つは,「事業者の関心は専ら処理価格にあり,処理の質はほとんど顧みられない」というものである。産業財取引のうち,原材料や部品などの物財の調達において,単純にコストを惜しむと事業者の作る製品の品質が下がることがあるので,事業者は,コスト・パフォーマンスに関心を持つ。しかし,マイナス価値の物質である産業廃棄物の処理に費用を投じても,事業者の経済的利益にはつながらないため,事業者は専ら処理価格を基準に産業廃棄物処理業者を選択するという理論である。この通念があるために,産業廃棄物処理サービスの取引に対しては取引の自由をある程度制限することも許容されるという了解があり,前述のような法規制がなされている。また,産業廃棄物処理業者の多くが,処理価格を唯一の競争手段としている。
2つ目は,「産業廃棄物処理に関する普遍的な価値基準が存在しない」という通念である。産業廃棄物処理サービスの買い手である事業者は,価格に関心を向けるのみであって,処理の質の良い悪いを判断しないとすれば,ここに価値基準はないと考えるのは当然である。また,産業廃棄物処理業者の間では,自己の処理だけが正当であるとの前提で,同業他社に対するネガティブキャンペーンが繰り広げられる傾向にある。こうした状況を受けて,業界団体が産業廃棄物処理の自主基準を作成し普及する努力を続けている。また,国が進める優良産廃処理業者認定制度においては,優良な処理の基準を設定することを断念し,産業廃棄物処理業者に情報を開示させることで代えているのである。
3つ目は,「産業廃棄物処理サービスにおいて,ブランドは大きな意味を持たない」という通念である。最初の2つの通念からは,産業廃棄物処理サービスは非ブランド品すなわち,コモディティとして市場取引されていることが推測できる。つまり,事業者は産業廃棄物処理業者を個体として識別せず,群として認識する複数の産業廃棄物処理業者の中から価格の最も安い者を選ぶと考えられているのである。また,実際に自社のブランドの確立に本気で取り組んでいる産業廃棄物処理業者は,未だ少数である。多くの産業廃棄物処理業者は,顧客である事業者から預かった産業廃棄物を目立つことなく処理することが,顧客に対する誠意であり,産業廃棄物処理業者としての美徳であると考えている。こうした状況に対して,優良産廃処理業者認定制度は,事業者が産業廃棄物処理業者を群(コモディティ)としてではなく,個別の存在(ブランド)として認識できるようにするために,情報提供の仕組みを提供することを目的としているのである。
(2) 通念に対する疑問
通念に基づいて,産業廃棄物処理業者は事業を進め,また行政は政策を展開している。しかし,通念についての疑問も感じられるところである。
まず,「事業者の関心は専ら処理価格にあり,処理の質はほとんど顧みられない」という通念に対しては,不適正処理への処罰規定が厳しくなり,事業者の意識が変わってきているのではないかという疑問を持つ。委託先の産業廃棄物処理業者が不適正処理をした場合に,委託元の事業者にまで責任が追及され,事業者名の公表などの措置がとられるようになった。そのため,事業者は企業防衛の目的から,産業廃棄物処理業者の選択に慎重になっているとも考えられる。もはや,事業者が産業廃棄物処理業者を選択するに際して,処理価格以外の要素をまったく検討しないことなどないだろう。そうであるならば,価格以外のどのような要素を検討の対象としているのか,検討の程度はどのくらいなのか等を知る必要があるだろう。
事業者の関心が処理価格以外の要素に対しても向かうということになるならば,第2の通念「産業廃棄物処理に関する普遍的な価値基準が存在しない」も修正が必要になる。事業者が,処理価格以外の要素を加えて産業廃棄物処理のコスト・パフォーマンスを比較検討するならば,コスト・パフォーマンスを算定するために価値基準が導入されるはずである。すなわち,事業者は,「価値ある処理とは何か」,「望ましい処理とは何か」といった価値基準を持ち,その基準にあてはめて産業廃棄物処理業者の価値を算定するのである。ただし,すべての事業者が同一の価値基準を持つということはないだろう。反面,各事業者の価値基準が互いにまったく異なるということもないだろう。それらについて,実態を知る必要がある。
第3の通念「産業廃棄物処理サービスにおいて,ブランドは大きな意味を持たない」は,多くの産業廃棄物処理業者がその処理価格の安さを唯一のアピール要素として,熾烈な価格競争をしている現状を見る限りでは妥当である。また,現実に産業廃棄物処理業者が派手な広告をすることは殆どないし,一般人が産業廃棄物処理業者のブランドを知ることも希である。このような状況を見れば,産廃処理ブランドの存在感が薄いことは理解できる。しかし一方で,産業廃棄物処理業者と事業者が,長期にわたる安定的な関係を構築している例も存在しているが,そのような例においては,顧客である事業者は,産業廃棄物処理業者をブランドとして認識し選択しているはずである。また,産業廃棄物処理業者との関係を維持している過程でブランドの認識は更に強まっている可能性もある。漠然と「ブランドは大きな意味を持たない」と理解するに留まらず,「ブランドはどの程度の意味を持っているのか」を把握したいところである。
以上,産業廃棄物処理業および政策の根底にある通念と,それらに対する疑問を論じた。これら疑問の原因は,産業廃棄物処理のマーケティング側面に関する知見が少ないことに帰せられるだろう。事業者が産業廃棄物業者選択する際に価格にしか関心が向かわないことは,理論的には肯定できるものではあるが,現実に事業者がどのように産業廃棄物処理業者を選択しているのかは未だに調査されていない。同様に,産業廃棄物処理業者のブランドについても,定量的な把握はなされていないのである。
脚注
(注[40])清水修二「廃棄物処理施設の立地と住民合意形成」『福島大学地域創造』,59巻4号,2008年,3-13ページ。
(注[41])六丸友章ら「廃棄物処理施設の立地と都市計画への位置づけに関する基礎的研究――エコタウン事業をケーススタディとして」『日本都市計画学会都市計画論文集』,46巻3号,2011年10月,367-372ページ。
(注[42])籠義樹『嫌悪施設の立地問題――環境リスクと公正性』(麗澤大学経済学会叢書),2009年。
(注[43])廃棄物処理施設の立地に関する経済学観点からの研究のトレンドについては,李友炯「廃棄物処理施設の最適供給」『応用経済学研究』,3巻,2008年,1-11ページに詳しい。
(注[44])廃棄物処理施設の立地問題および合意形成についての事例の記述例としては,中澤高師「廃棄物処理施設の立地における受苦の分担と重複」『社会学評論』,59巻4号,2008年,787-804ページや,清水の前掲論文のほか,1990年代から多くの報告が提出されている。
(注[46])環境省『産業廃棄物の不法投棄等の状況(平成24年度)について』,2012年。
(注[47])冨田悟「わが国における産業廃棄物の不法投棄等の現状と対策」『いんだすと』,23巻5号,2008年,6-12ページ。
(注[48])青森岩手県境事案の原状回復作業の事業費は,両県合わせて716億円にものぼる。
(注[49])能代事案をひとつの契機として,秋田県は「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例(平成16年)」を規定することになった。秋田県には旧鉱山の資本・技術・敷地を活かした有力な産業廃棄物処理業者があり,広く全国からの産業廃棄物を処理してきたが,新たな規制が事業の障害になっている面がある。
(注[50])石渡正佳『産廃コネクション』,WAVE出版,2002年,18-36ページ。
石渡正佳『不法投棄はこうしてなくす-実践対策マニュアル-』(岩波ブックレットNo.598),岩波書店,2003年,27-43ページ。
(注[51])田崎智宏ら「不法投棄が発生しやすい地理属性とその発生確率の解析」『廃棄物学会論文誌』,15巻1号,2007年,1-10ページ。
古市徹ら「廃棄物の不法投棄対策への総合的・体系的アプローチ」『廃棄物学会誌』,18巻2号,2007年,77-88ページ。
(注[52])春山成子,内海真希「都市近郊での産業廃棄物施設集中についての空間分析」『歴史地理学』48巻3号,2006年,1-19ページ。
(注[53])春山らの研究では,産業廃棄物処理施設が集中した土地として,埼玉県南部のくぬぎ山三富地区を挙げている。ほかにも,関東から比較的近く,またその場所自体が工業集積地である福島県いわき市が,いわゆる産廃銀座の例として挙げられることが多い。しかし,それらの産廃銀座においても,産業廃棄物処理施設が軒を連ねているとか,周囲に何本もの焼却炉煙突を一望できるとかの状況ではない。筆者の体験では,ある施設から自動車で10分走って次の処理施設,さらに15分走って次の施設,という程度の密度である。
(注[54])公益社団法人全国産業廃棄物連合会のパンフレットから。
(注[55])上田晃輔「産業廃棄物処理についての諸問題」『技術と経済』,284号,1990年,25-31ページ。
(注[56]) このことは,第2章の図 14に示したバッズ取引の構造を参照することで理解しやすい。
(注[57])産業廃棄物の積み込みを夕方に終えた車両が翌朝に遠方の処理施設に向かう場合,車庫での一晩を保管行為にあたるとし,車庫を産業廃棄物積替・保管施設として届出するよう求める行政もある。
(注[58])法律は,産業廃棄物の処理を業者委託する際に産業廃棄物管理票,通称マニフェストを用いることを規定している。電子マニフェストは,紙の管理票に代わってインターネットを利用して産業廃棄物の行方を管理するシステムで,法律にもとづいて国が指定する全国1カ所の機関が運営している。
(注[59])産業廃棄物処理業者優良化推進事業の詳細,特にそのコンセプトは,北村喜宣「産業廃棄物処理業優良化推進事業の経緯と今後」『いんだすと』,20巻5号,2005年,2-6ページ及び,北村喜宣「産業廃棄物処理業優良性評価基準適合認定制度と2010年改正法」『いんだすと』,25巻5号, 2010年,32-36ページに解説されている。
(注[60])産業廃棄物処理業優良化推進事業では,許可を受けた産業廃棄物処理業者のうち,(1)遵法性,(2)情報公開,(3)環境マネジメントシステムの3つの観点から設定された評価基準に適合する者に対して,行政的な優遇を与える。3つの観点のうち,特に重視されているのは,情報公開である。所定の項目について,インターネットで情報公開することが必要とされており,これによって産業廃棄物処理業者に関する情報を事業者が入手しやすくなるとされている。優良産廃処理業者認定制度では,これら評価項目に2項目が加えられた。
(注[61])千葉泰忍「平成19年度の産業廃棄物事犯の取締り状況について」『いんだすと』,23巻5号,2008年,16-19ページ。
冨田悟「わが国における産業廃棄物の不法投棄等の現状と対策」『いんだすと』,23巻5号,2008年,6-12ページ。
牧谷邦昭「産業廃棄物の不法投棄等の現状と対策の動向」『廃棄物学会誌』18巻2号, 2007年,71-76ページ。
(注[62])細田衛士『グッズとバッズの経済学—循環型社会の基本原理』,東洋経済新報社,1999年,107-111ページから,バッズ取引における情報伝達の問題点に関する記述を引用する。
取引においてモノと貨幣が同じ方向に流れる場合,取引を重ねるにつれて情報が拡散するおそれがある。この場合,逆有償で費用を受け取るが,一方で適正な処理をせずに投棄したり埋め立てたりする動機が存在する。とりわけ適正処理やリサイクルする技術や知識がない主体がバッズを扱えば,いきおい処理が不適当になるのは理の当然である。
バッズを引き渡す主体,すなわちバッズの処理を依頼する主体は,貨幣を支払うと同時にバッズも取引相手に渡してしまう。それがどのように処理されるか,再資源化の内容がどうであるか,受け取った主体はもちろんよく知っている。しかし,引き渡した主体にはこうした情報は伝わりにくい。
(注[63])余田拓郎,首藤明敏『B2Bブランディング – 企業間の取引接点を強化する』,日本経済新聞社,2006年,58-59ページから,産業財の購買プロセスに関する記述を引用する。
購買プロセスは,大きく分けて「案件化」と「取引先選択」の二つのステージからなる。ビジネスのソリューション化に伴い,成熟度の高い産業でも新たに課題を認識し需要が喚起される機会が拡大しており,昨今では,とくに案件化段階がカギとなることが多い。B2B企業にとっては,顧客企業に案件化を促しておくことで,それに続く取引先選択地に自社を選んでもらいやすくなる。ただし,案件化を促さなくても,要件規定の支援などをおこなうことで,取引先選択地に優位性をあらかじめ築いておくこともできる。
(注[64])細田の前掲書35-37ページから,環境規制の必要性に関する記述を引用する。
環境に対して何ら規制や制約のない経済では,静脈技術の採用は多くの個別企業にとって利益をもたらすものではない。もしそれが収益性をあげるような技術であれば,それは本質的に動脈技術であろう。そのような技術の採用については,市場の競争に任せておけば十分である。バッズを処理ないし再資源化する静脈技術は,何らかの規制や制約があってはじめて顕在化するのである。ある物質がグッズになるかバッズになるかは,需給のバランスによって決まり,しかもその需給のバランスは制度的な枠組み(レジーム)に依存する。
(注[65])細田の前掲書199-120ページから,バッズ市場の問題点に関する記述を引用する。
情報の非対称性を悪用した業者はヒット・エンド・ラン方式で不法投棄や不適正処理を行い,市場から逃げていく。つまり無制約な参入・退出があるためにこうしたことが起きてしまうのである。グッズの世界ではこうした自由な参入・退出が市場の効率性を保証するのだが,バッズの世界ではそうはいかない。自由な参入・退出のことをオープンアクセスというが,このオープンアクセスがグッズとバッズの取引では異なった結果をもたらすという事実の認識は重要である。
(注[66])平成7年に公布された容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)は,自治体が分別収集した容器包装廃棄物を事業者(容器メーカーや飲料メーカー等)に引き取らせ,再商品化を行うことを規定している。事業者の責務を代行するために,事業者が資金を拠出した指定法人「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」が設置されている。
拡大生産者責任に拠る容器廃棄物回収の仕組みは,材料リサイクルの促進を目的とするならば妥当であろうが,廃棄物処理の本来の目的である公衆衛生の向上と生活環境の保全という観点からは,最適ではない。

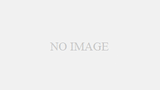
コメント